全国地方銀行協会の会員は「銀行法により免許を受けた銀行であって、主たる営業基盤が地方的なもの」で、なおかつ「加入につき会員総会の承認を得」たものだと、同協会の定款には記されています。
一方の第二地方銀行協会の会員は、やはり定款によって「この協会の会員は、平成元年2月1日以降、金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和43年法律第86号)第6条第5項の規定に基づいて銀行法により免許を受けたとみなされた銀行及び会員から営業を譲り受けることを目的として新たに免許を受けた銀行であって、主たる営業基盤が地方的なもの」で、なおかつ「理事会の承認を得」たものとされています。
少し難しい表現になっていますが、ここでいう「銀行法により免許を受けたとみなされた銀行」とは、相互銀行から転換した銀行のことです。
つまり、地方銀行と第二地方銀行ではその成り立ちにも違いがあり、第二地銀の大部分がこの相互銀行から転換した銀行であるのに対し、地銀のルーツは日本初の銀行である第一国立銀行の誕生以降、数多く誕生した国立銀行である場合が少なくありません。
バブル崩壊以降加速する再編の波
この成り立ちも影響し、地銀は地域に大きな影響力を持ち、各都道府県や市町村などの自治体の指定金融機関として、公金の収納、支払の事務を取り扱う場合も多くなっています。
規模の面でみても、第二地銀は地銀よりも小さいところがほとんどです。そのため、第二地銀は地銀よりもバブル崩壊、金融危機の影響を大きく受け、1989年末には68行あったものの、2025年1月時点では再編などによって36行にまで減少しました。
それに対して、地銀は同じく1989年末の64行が2025年1月時点では61行と、こちらは3行の減少にとどまりました。ただし、長らく続いた「ゼロ金利」「マイナス金利」の影響もあって、経営環境は依然として厳しく、再編の波は現在進行形であるといっていいでしょう。
例えば、2026年にはどちらも長野県に本店がある地銀の八十二銀行と第二地銀の長野銀行が合併して八十二長野銀行に、2027年には荘内銀行(山形県)と北都銀行(秋田県)が合併してフィデア銀行となる予定です。
そのほかにも、水面下でさまざまな再編の動きがあるといわれています。つまり、地銀も第二地銀もさらなる減少が見込まれるわけです。
加えて、近年は地銀、第二地銀が持株会社を設立するケースが増えています。例えば、ふくおかフィナンシャルグループは傘下に地銀の福岡銀行(福岡県)、十八親和銀行(長崎県)、第二地銀の熊本銀行(熊本県)、福岡中央銀行(福岡県)などを抱え、コンコルディア・フィナンシャルグループは地銀の横浜銀行(神奈川県)、第二地銀の東日本銀行(東京都)、神奈川銀行(神奈川県)などを抱えています。



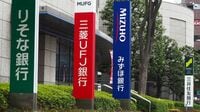



























無料会員登録はこちら
ログインはこちら