ついに台湾企業の傘下へ、"第2のソニー"になり損ねた「音響の名門」パイオニアがたどった蹉跌
1990年代後半に登場したプラズマ技術は、大画面・高コントラストといった特性を生かし、液晶よりも先行して高級モデルや大画面テレビの市場でシェアを伸ばした。ところが、2000年代に入ると液晶テレビが、液晶技術の進化、とくにフルHD対応や低消費電力を強みとし、コスト面での優位性を武器に主流となった。
両者は同時期に登場し、それぞれ異なる技術的強みと市場特性に対応して進化を競い合った。パイオニアはプラズマ技術の優位性を信じ、これに大規模な投資を行った。
ただ、液晶が急速な技術革新と圧倒的な低価格化などの強みを発揮したのに対して、プラズマは弱点である消費電力の多さが顕在化。激しい価格競争に巻き込まれた。その結果、2008年にはPDPの生産からの撤退をせざるをえなくなった。「選択と集中」が裏目に出た格好だ。
この自社製PDPを使った垂直統合型のプラズマテレビ事業の挫折は、パイオニアの経営に大きな打撃を与えた。2000年代半ばに1兆円を目指した売上高は、2024年3月期には2415億円まで縮小。家庭用AV機器からも相次ぎ撤退した。
「コア・コンピタンスの再構築」という課題
ソニーが音響映像事業を継続しつつ、ゲーム、音楽、映画、半導体、金融(ソニーフィナンシャルグループは9月に分離・再上場)など、多様な事業分野を柔軟に展開することで収益源を多角化していったのとは対照的だ。ソニーは、ある事業が苦境に陥っても、ほかの事業でそれを補うことができる強さを持っていた。
一方、パイオニアはプラズマテレビにおいて、高画質による「差別化戦略」を追求したが、液晶テレビが「コストリーダーシップ戦略」で急速に市場を席巻した際、パイオニアは差別化の優位性を保ちつつ、コスト競争力を備えるという「スタック・イン・ザ・ミドル(中途半端な状態)」に陥ってしまった。結果的に、どの戦略も徹底できず、市場での存在感を失っていった。
パイオニアのコア・コンピタンス(他社がマネできない、核となる能力)は「音」と「映像」に関する卓越した技術力にあった。デジタル化やコモディティー(汎用品)化といった市場変化の中で、このコア・コンピタンスをいかに再構築し、新しい時代に適合させるかという課題に直面した。
プラズマ技術への固執は、リソースの集中を招き、新たな市場ニーズへの対応を遅らせたと考えられる。近年、注目されている既存事業の深化と新規事業の探索を両立させる「両利きの経営」を怠っていたといえよう。
(後編に続く)
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら


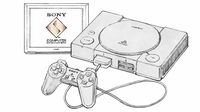



























無料会員登録はこちら
ログインはこちら