消費者の不買運動の可能性がある。またもっと怖いのは内部の従業員からの反発だ。離反する従業員がいたら大きなコストになってしまう。
企業はどんなふうに向き合うべきか
ここで大げさな話になるが、たんにセブンの話ではなく、企業全体の話として次を提案したい。
①地政学リスクガバナンスの確立。台湾の表記問題は、マーケティング部門やウェブデザイン担当者が処理すべきエラーではない。取締役会レベルで議論されるべきだろう。企業は、これらの問題を専門に議論し、対応策を策定する部署や役員を設置する必要がある。
②シナリオ作成。「もし中国政府が特定地域の呼称について、ある名称を使うよう要求してきたらどうするか」「もし自社の役員が政治的な失言をしたらどうするか」これらは戦略的に考えておくべきだろう。もちろん「もし台湾の緊張が高まった場合どうするか」といった地政学的なシナリオも事前に準備しておくべきだろう。
③表現の戦略性。企業は政治的に微妙な地理の場所については、最大限の中立性を追求するべきだろう。だって商売なんだもん。台湾をどう記述するか、政治的な色の薄い言葉を、ずっとずっとずっと見つけ出そうと努力せねばならない。
セブン&アイホールディングスの台湾記述をめぐる炎上は、さまざまな示唆に富む。中国が主張する「一つの中国」と、企業が選んできた「戦略的曖昧さ」とのあいだに埋めがたい溝があるからだ。
コンビニではレジで「お弁当温めますか?」と聞かれるが、本来は「国家同士の関係、温め直しますか?」と提案される必要がある。みなさんへお願い。企業もがんばっているから、記載の齟齬があるかもしれないけれども、たまの失敗は許してやって。
台湾は大切なパートナーだって、誰もがわかっているから、内輪を批判するのは得策じゃない。分断が広がるのは、私たちを利しないと感じている。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

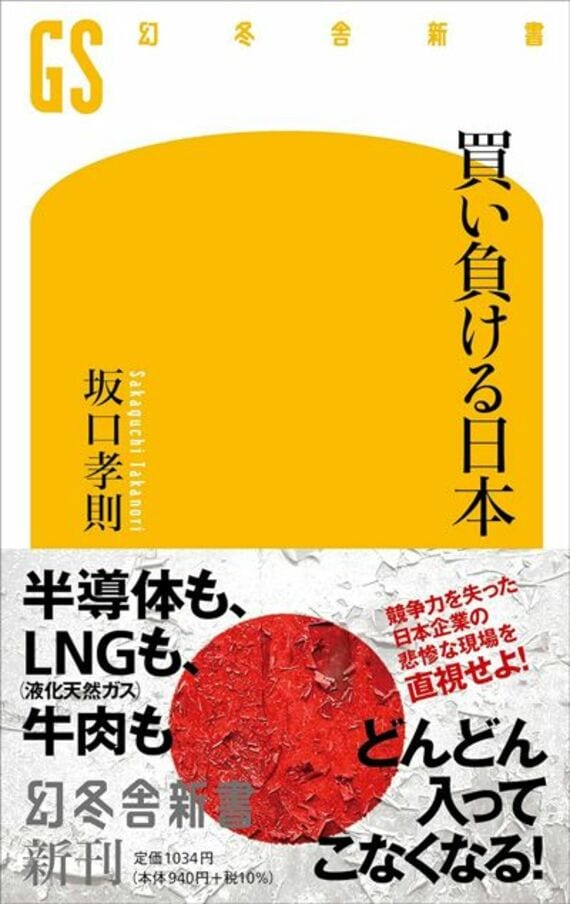


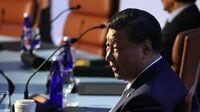



























無料会員登録はこちら
ログインはこちら