
「子どもたちが姓を変えるのを嫌がった」(60代女性)
首都圏の会社で働くイトウアキコさん(60代女性、以下すべて仮名)が、4年制大学を卒業して就職したのは、ちょうど男女雇用機会均等法ができた時期だ。寿退社が当たり前で、25歳を過ぎて未婚だと売れ残りと呼ばれる時代。「社内で出会った夫と結婚して、当たり前に夫の姓に改姓しました」。
その後、夫はうつ病を患い職を転々とした。アキコさんがパートで働き始めると「なぜ自分を置いて働きにいくんだ。死んでやる」と激高し、アキコさんや子どもたちに当たるようになった。約10年前、夜逃げのようにして子どもたちと家を出た。
別居だけのつもりだったが、夫のうつ病はひどくなり、長い協議を経て離婚した。当時、中学生から大学生の子どもたちは姓を変えるのを嫌がった。アキコさんも、旧姓よりも婚姻時の姓でいる年数の方が長くなっていた。名義変更の手間も膨大だ。
男性を家の長とするシステム
アキコさんは婚姻時のままの姓を続けることにしたが、それを夫には伝えていない。離婚調停をしていたとき、夫がアキコさんに「離婚するならイトウ姓は名乗るな」と言い出したことがあったからだ。
「夫婦同姓制度は、男性を家の長とするシステムです。夫の姓に改姓するのが当たり前だし、夫からすると、妻が自分の姓を名乗るということは、自分の傘下に入るようなものだと感じるのでしょうね。息子の妻には、本当に姓を変えていいのかと確認しました」
「改姓したから両親の墓に入れない」(50代女性)
関西に住むワタナベヒロミ(50代女性)さんは、約20年前、2人の子どもを連れて離婚した。「子どもたちに負担をかけたくなくて、婚姻時の姓を続けることにしました」。戸籍から除籍して、新しい戸籍を作り、子どもたちを新戸籍に移した。

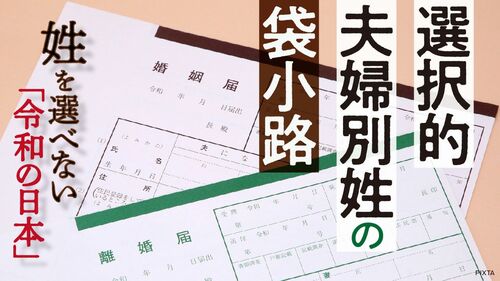

































無料会員登録はこちら
ログインはこちら