社会を「希望の分配のメカニズム」と捉えた人類学者ガッサン・ハージは、希望の不足によってあらゆるところに脅威を見出すような「防衛的な社会」が生まれると主張したが、それを「憂慮すること」「憂慮する人々」という言葉で言い表した。「操作されている」「剥奪されている」といった疑心暗鬼の高まりだ(『希望の分配メカニズム パラノイア・ナショナリズム批判』塩原良和訳、御茶の水書房)。
参政党の政策は「憂慮する人々」へのアピール
つまり、国家や政治家は、まともに働き納税している人々に報いるどころか、さらなるリスクと負担を押し付けようと目論んでおり、将来に希望の持ちようがない。このような収奪的な構造の固定化と関係性は、国民であることがむしろネガティブな意味合いを帯びてしまう。
参政党の“3つの柱と9の政策”にある「日本人を豊かにする」「日本人を守り抜く」「日本人を育む」という表現を見ると、政策の主語にすべて「日本人」が入っているのは、まさに「憂慮する人々」へのアピールであり、ポジティブへの反転を意図している。
前出の記事で紹介した反既得権益型のポピュリズムは、エリートや既存の政党を一般の民衆と敵対させる構図を作るところに特徴があるが、参政党の場合、エリートや既存の政党の向こう側に潜むラスボスのような「外国勢力」が持ち出されることが多い(神谷代表の過去の著作では「国際金融資本」「ビッグ・ファーマ」などと名指しされている)。
「防衛的な社会」については、ハージは、「彼・彼女らは、自らと自らが属するネイションの関係が脆弱であることに由来する恐怖を、異邦人と分類されるあらゆる人々に対して投影する」と述べているが、ここには国民自体が「内なる難民」と化しつつある現状が露呈している。
と同時に、このような事態が出来したのは、やはりこの「失われた30年」を抜きに考えることはできない。
そう、ポピュリズム政党の台頭は、いわば社会の危機を告げ知らせる「炭鉱のカナリア」なのだ。それによってわたしたちはむしろ問題の本質に立ち戻らなければならない。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

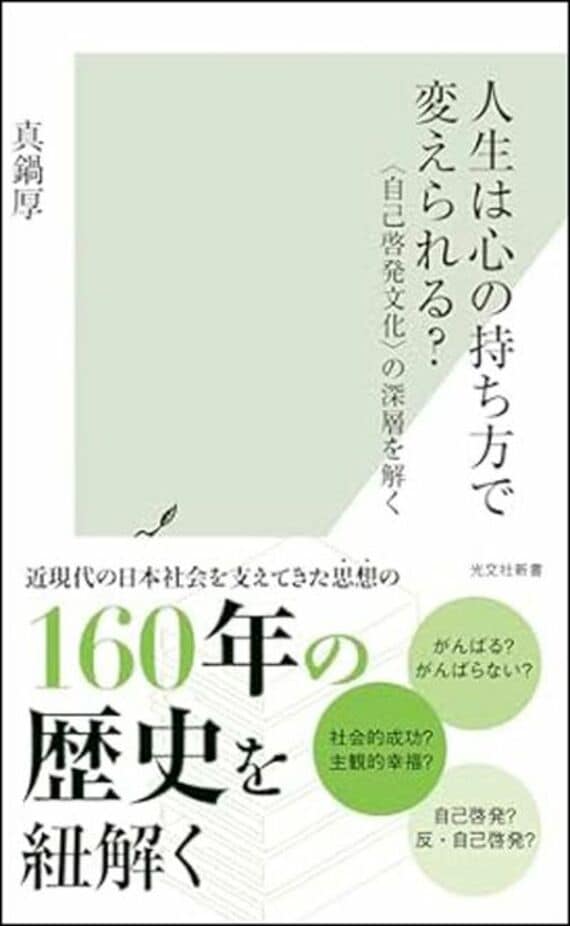






























無料会員登録はこちら
ログインはこちら