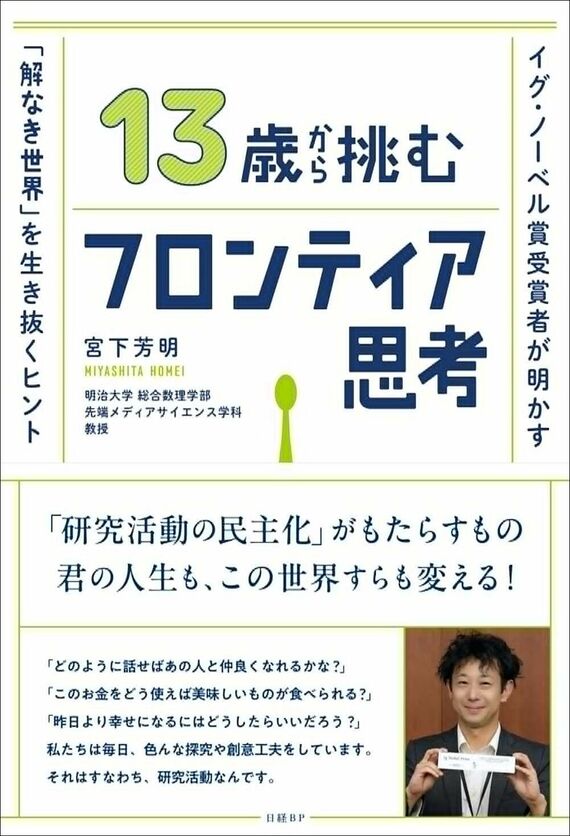宮下:一概には言えませんが、多少はあるかもしれないですね。もちろん小・中・高等学校では、考える力を身に付けられるようにと教育を受けていると思いますが、受験勉強を経て、意外とそれが反映されていないなと感じることはあります。
とはいえ、大学は学生たちの問題解決能力を育成するところでもあるので、多少、「答えがない問い」を考える力が不足していたとしても、4年間の教育や研究活動を通して身に付けることはできるはずです。
窪田:問題解決能力は、大学で伸ばしていけると。
宮下:はい。それが学生を社会に送り出すまでの大学教育の使命だと思っています。
窪田:先ほど研究の話をしましたが、私は小学生の時にアメリカと日本の両方で教育を受けていて、一番衝撃だったのが日本では「答え」しか聞かれないことだったんです。先生に質問されて、それに答えるだけ。アメリカではいかにたくさん質問するかが勝負でしたが、日本で同じことをすると「授業の妨害になるからやめなさい」とさんざん怒られました。
だから、日本ではすごく成績が悪くて。でも、アメリカに行って「何でそうなるの?」「どうしてそう考えるの?」と、とにかく質問をしていたら、「すごいね」と褒められる。いきなり成績優秀な生徒になりました(笑)。
答えは調べればわかる。問いの立て方が重要
宮下:授業が「問い」から始まっているんですね。
窪田:逆に言うと、答えは調べればわかるから、そんなに重要じゃない。問いの立て方と、解答するまでのロジックの組み立て方が重視されていました。
宮下:暗記ではダメなんですね。
窪田:そうなんです。子どもに考えさせる教育ですよね。私の人生は、幼少期にアメリカで教育を受けたことで大きく変わったと思っています。
宮下:アメリカに行っていなかったら、窪田先生のような研究者は生まれなかったかもしれないですね。