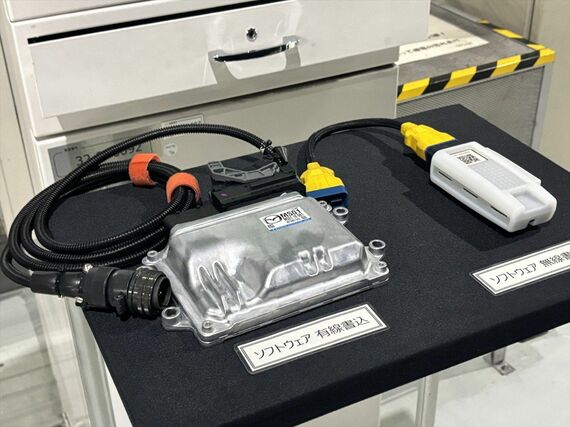
ここまでの視察内容を踏まえると、マツダが以前から主張している「われわれにはEV専用工場は必要ない」という考え方が、現実に可能であることが理解できる。
H2では、EVの需要変動を吸収できる生産構成に向けた準備が、すでにできているからだ。
仮に、EVシフトが一気に進んだとして、H2に流れるすべてのモデル・グレードがEVになっても対応できる。
ただし、現実的には、そう簡単に進まないだろう。いわゆるトランプ関税に対して、日米政府間の交渉が今後、どのような着地点を見いだすことができるかわからないが、追加関税が完全撤廃されるシナリオは想像しにくい。
その場合、マツダとしてはアメリカ向けの完成車輸出のあり方を大幅に見直さなければならず、すでにマツダ幹部は「柔軟性を持った対応が必要だ」という発言を公の場でしている。
トヨタとの合弁工場やメキシコ工場はどうするか?
マツダはこれまで、市場動向に応じて国や地域を越えて、生産拠点間で需要を互いにコントロールする「スイング生産」を実施してきた。
これをアメリカ向けに行うとすると、売れ筋商品である「CX-5」の一部を本社工場から、また防府工場から「CX-70」と「CX-90」をトヨタとの合弁事業であるアメリカ・アラバマ州「マツダ トヨタ マニュファクチャリング USA」に移管することが考えられる。

現在、アメリカでは「CX-50」の販売が好調だが、そこにさらに混流するとなると、当然だがトヨタとの調整が必要になる。また、ラージ商品群のために、H2のような大幅な施設改良をマツダ単体で行うことも考えにくい。
また、メキシコの「マツダ・デ・メキシコ・ビークル・オペレーション」で生産する車両の約3割を占めるアメリカ向け輸出を、どうスイングさせるのか。
今回のH2の現状と、今後のH2での展開をベースに、トランプ関税対応のスイング生産を考えると「選択肢はあまり多くない」という印象を持った。































無料会員登録はこちら
ログインはこちら