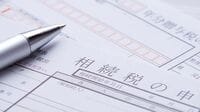「子どもや孫への贈与はどうすれば?」新年度入りで知っておきたい<暦年贈与><相続時精算課税>の徹底比較と、昨年お得度が増した新ルール
よって、毎年その都度、学費を納めるタイミングなどに必要な分だけを援助するのが理想です。
ただ健康状態や認知機能の低下などの心配があって、元気なうちにできるだけ早くまとまった金額を贈与しておきたいという場合は、「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」という制度を活用すれば、最大1500万円までの贈与は非課税となります。
ここで、注意したいのは、30歳までに使いきれなかった場合には、その残った金額に対して贈与税が課税される点です。さらに、この制度は来年(2026年)3月31日までの期限付きとなっており、活用したい場合には、金融機関に相談し、専用の口座を開設する必要があります。
生活費や教育費以外にも使えるお金を贈与したい場合
入学祝いやお年玉、お小遣いのように、何に使ってもよいお金を一定の範囲内で贈ることについては、もちろん贈与税はかかりません。ただし、その金額が、子ども(あるいは孫)1人につき年間110万円を超えてしまうと贈与税がかかってきます。
すなわち、年間110万円以下の贈与であれば課税されないため、この仕組みを利用して、毎年(1月1日〜12月31日までの間に)贈与を行う方法が「暦年贈与」といわれるものです(110万円を超える額を暦年贈与する場合には贈与税の申告と納付が必要です)。
毎年110万円以下であれば、申告も不要で特に複雑な手続きも必要ないため、もっとも活用されることが多い制度ともいえますが、いくつかおさえておきたい点があります。