【EUが国防費増でも潤うのは米国の防衛産業?】米国と分断深める欧州NATOの「揃わぬ足並み」。欧州にとって米国の背中はこれほど遠い
それと同時に、EUの防衛装備品市場が加盟国ごとに細分化されている点を指摘している。もちろん各国も、そんなことはよく分かっている。それでも「国際共同開発」の参加国にしてみると、各国での防衛産業育成策と切り離すことはできない。
「過剰な独自の運用要求」
少しでも多くの作業分担を確保し、自国製部品の採用を働きかけるのは人情だ。先にも述べたように、国際共同開発の行き先は我田引水であり、ここでも総論賛成・各論反対は避けられない。
「欧州防衛産業戦略」では、2030年までに域内で調達する防衛装備品の4割以上を国際共同開発にするという数値目標を掲げている。注目すべきは、この数値目標と並行して「過剰な独自の運用要求」を諫(いさ)めていることだ。
国際共同開発に際して、各国が産業保護の観点から自己主張を譲らないことが障害になっていることは、何度となく指摘されてきた。ただし防衛装備品である以上、軍の「運用要求」は「聖域」だった。
この「過剰な独自の運用要求」のため、せっかく共同開発しても各国ごとに細部が異なってくる。これは開発費高騰の原因となるうえに、部品互換性などの相互運用性にも支障が生じる。軍にとっての聖域である「運用要求」にも自粛を求めざるを得ないほどまでに、EUは防衛産業基盤維持の困難に直面している。
アメリカの「国家防衛産業戦略」でも、「過度な要求仕様の抑制」を求めていた。各国の財政・防衛産業事情は「背に腹はかえられない」ところまで来ているので、軍も「弘法筆を選ばず」でいけということだ。
こうした中で「欧州防衛産業戦略」では、防衛関連の中小・中堅企業育成を重要項目として取り上げている。防衛装備品の供給網(サプライチェーン)維持において中小・中堅企業は重要な構成要素であること、さらには中小・中堅企業にはスタートアップとして革新的な技術開発が期待されることなどが主な要因だ{※EUの「欧州防衛産業戦略」については、清岡克吉「「欧州防衛産業戦略」を読み解く」『NIDSコメンタリー』第326号(2024年5月)も参照のこと}。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

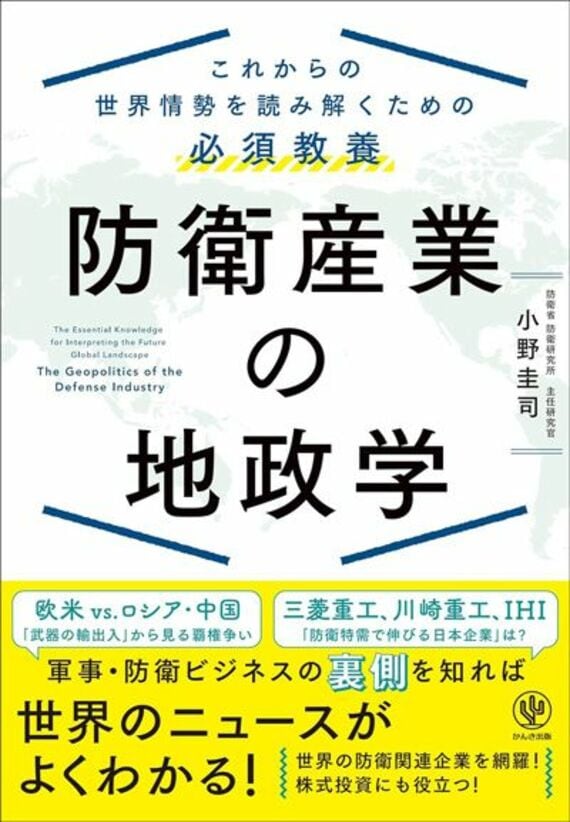






























無料会員登録はこちら
ログインはこちら