生成AIが引き起こす深刻な「電力不足」解決のカギ 検索エンジンと比べても生成AIは電力爆食
ただ、節減できるとはいえ「適材適所」のシナリオであっても電力消費は大幅に増大する。これに国内の電力供給は応えられるのだろうか。
昨年12月に第7次エネルギー基本計画の案が公表された。そこで示されたメインシナリオにおいては、40年度に国内の総発電電力量は1.1兆〜1.2兆キロワット時に増加する(23年度の0.99兆に対し、約1〜2割の増加)。増加した電力需要は、火力3〜4割、原子力2割、再生可能エネルギー4〜5割の電源構成によって賄われる見通しである。
需要増に対して、DCなどICTセクターがどの程度影響するのかは明らかにされていないが、計画策定に貢献した複数の機関の推計では、おおむね1000億キロワット時以内(総需要に対して約1割以内)と見込まれている。この範囲で収まる場合には、国の計画どおりに脱炭素電源の開発が進めば供給不足は生じないことになる。
一方でリスクシナリオへの対応には懸念が残る。当社試算では、省電力技術開発が進まない中でモデルの大規模化が進行すれば、ICTセクター電力消費は5000億キロワット時超に上振れする。この場合には大幅な電力供給不足に陥る可能性がある。
脱炭素電源による供給計画が上限に達しているとすれば、リスクシナリオの需要上振れ分は火力のたき増しなどで手当てする必要があるだろう。脱炭素化による制約や送電網の容量不足などで十分な手当てができなければ、DCの国内立地は制約を受けることになる。DCや関連産業の国外流出による国富の流出や、経済安全保障上の懸念が生じる可能性がある。
地理的な不均衡も懸念
総需給の不均衡だけでなく、地理的な不均衡も懸念される。現状でDCの8割以上は東京・大阪圏に立地しており、今後の立地計画も同エリアに集中している。一方で、今後増加が見込まれる脱炭素電源の立地は全国に分散している。このままでは、増加するDC電力需要を脱炭素電源にマッチさせることが難しい。








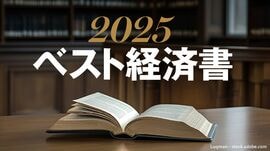




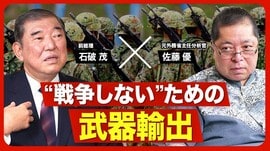

















無料会員登録はこちら
ログインはこちら