生成AIが引き起こす深刻な「電力不足」解決のカギ 検索エンジンと比べても生成AIは電力爆食
同じテキスト情報処理でも、従来型のウェブ検索に比べて生成AIの回答処理ははるかに多くの電力を消費する。画像や動画の入出力などに対応するマルチモーダル化が進めば、電力消費はさらに増大していく。
2つ目の要因はAIの社会浸透だ。22年に登場し、生成AIブームの火付け役となったChatGPTに続き、今後は自律性を持つAIエージェントが普及し、さらに多くの知的タスクがAIに代替されると予想されている。自動車やドローン、ロボットなどの機械もAIで制御され、AI同士が自律的に会話する世界になれば、AIの利用機会は莫大なものとなるだろう。
生成AIの大規模化と急速な社会浸透が両輪となって、従来とは比較にならないほどの大量の計算処理が発生する。これが生成AIの電力消費問題の根本にある事象である。
電力供給は間に合うか
では具体的にどの程度の電力が必要となるのだろうか。長期の予測は極めて難しい。生成AIの大規模化が進む一方、電力の供給問題があることが広く認知された結果、電力を節約するための技術開発も進んでいるからだ。すべての用途で最先端のAIを使う必要はない。例えばスマートフォンに実装され簡便な機能を提供するAIは、省電力性を優先して小型化されていくと予想される。
当社では、超大規模(パラメーター数が数兆〜数十兆)から小規模(数百億未満)までさまざまな生成AIが開発され、省電力性も考慮しながら「適材適所」で活用されていく蓋然性が高いと考えている。そうした工夫により電力消費を節減できる。
あらゆるユースケースで超大規模AIを使うと仮定すると、当社の試算ではICTセクターの国内の電力消費は40年に最大で5480億キロワット時(20年比では27倍)となる。これに対し省電力を考慮した「適材適所」のシナリオでは560億〜1700億キロワット時(20年比では3〜9倍)へと、大幅に節減可能だ。







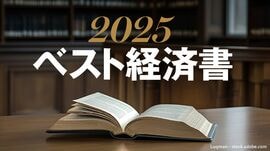
























無料会員登録はこちら
ログインはこちら