東大生があえて「ChatGPT」を課題で使う納得の訳 宿題で使うのはアリ?教育とAIの向き合い方
例えば「第六次産業化は農家の経営の多角化を推進する」と書いてあったとして、「経営の多角化か、確かにそれはありそうだな。じゃあ、経営の多角化の具体的なパターンはなんだろう?実際の実例はどんなものがあるんだろう?」と考えていくのです。
そしてChatGPTに「第六次産業化による経営の多角化についての実例を調べたいのですが、どのサイトで調べればいいでしょうか?」というように聞いてもいいのです。宿題をする参考としてChatGPTを利用していくことで、よりクオリティの高い回答を作ることができるようになるというわけですね。
ChatGPTを使うことのデメリットは、「自分で考えなくなること」です。自分の頭で考えるのではなく、ChatGPTに考えてもらうことになるので、勉強にならないというのがマイナスポイントです。
逆にいえばChatGPTを「自分で考えるためのツール」として使うのであれば、このデメリットは解消されます。
「どう考えるのか」にChatGPTを使う
先ほどの東大生たちの使い方のように、頭の整理に使ったり、骨子の部分を作るために使ったり、「どう考えるべきか」の手段を調べたりするのに使うのであれば、ChatGPTを使っても十分勉強の役に立つといえるわけですね。
ChatGPTを頭ごなしに禁止するのではなく、どのようにしてChatGPTを使いこなすべきなのか、ということを指導するような教育が求められるようになってきているとの考えから、ChatGPTの使い方を指導する学校も増えているようです。
ChatGPTを使うことを前提にして授業や課題を設計する学校もあります。とある学校では、「ChatGPTをこういうふうに使って、読書感想文を作りなさい」という課題を出しているそうです。ChatGPTを使うことを推奨して、宿題を出しているわけですね。
実際、これからの世の中においてテクノロジーを使いこなすための勉強は重要です。
もちろんコピー&ペーストして終わりでは、自分の頭で考えていることになりませんから、勉強になりません。しかし、ChatGPTを使いながら自分でも考えてみるという姿勢があれば、むしろ使わないよりも何倍も勉強になるかもしれないのです。ぜひこの点を意識してみてください。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

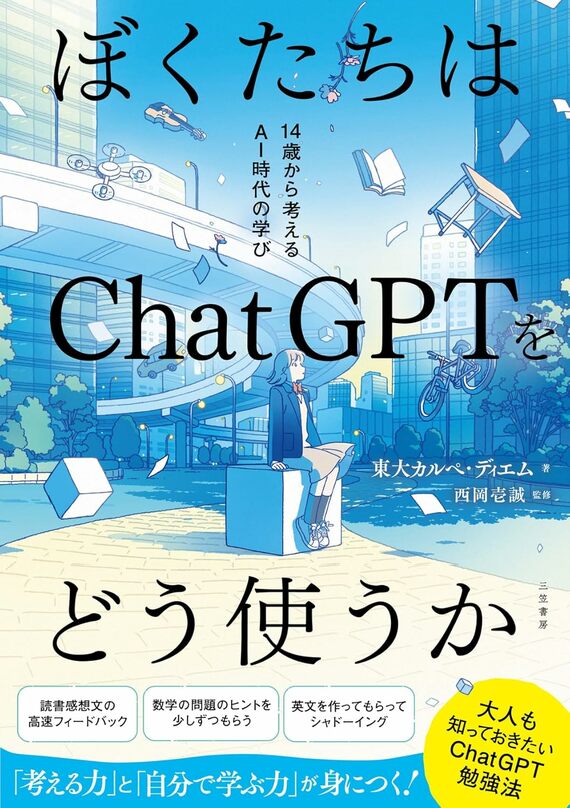
































無料会員登録はこちら
ログインはこちら