日産の暗闘史が示す「2度目の身売り」の背景 1999年の経営危機時と重なる既視感の正体
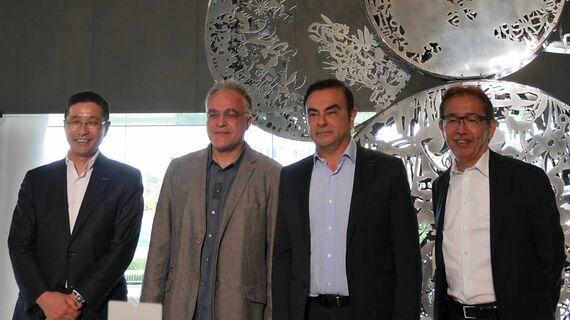
![週刊東洋経済 2025年2/1号(自動車 大再編時代)[雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/51EFFxfAJ6L._SL500_.jpg)
日産自動車とホンダが経営統合すれば、ホンダによる日産救済の一面があることは否定できない。日産からすれば1999年の経営危機時の仏ルノーによる資本参加以来の、「2度目の身売り」といえる状況だ。
そもそも日産はなぜ、再び経営危機に陥ったのか。筆者は1998年、朝日新聞経済部記者として日産の担当をしていたとき、倒産の足音が迫っているのをひしひしと感じた。今回の業績不振の構造的な要因については既視感がある。
日産には社内抗争の「遺伝子」がある。会社の業績や成長よりも、社内の権力争いに執着することで、危機を招いてきた。その歴史をひもといてみよう。
経営判断に労組が関与
戦後、日産が見舞われたのは労使間の激しい争いだった。そこで左派系労働組合を潰すために、1953年、日本興業銀行から日産に転籍していた専務取締役の川又克二氏が中心となり、会社寄りの第二労組を設立した。

川又氏が社長に就いてから4年後の1961年、新労組の委員長に塩路一郎氏が就任。「川又─塩路」の労使蜜月関係が始まり、役員人事も含めたあらゆる経営判断に労組が関与するという異様な体制になった。
転機は1977年、社長に石原俊氏が就いたことだ。石原氏は労使蜜月関係との決別に乗り出し、会長職にあった川又氏と労組への対応をめぐって対立関係となった。
川又氏が相談役に退く1983年までに、社内には会長派と社長派が存在。そこにまだ権勢を誇る塩路氏も介在して社内は混乱した。
生産のグローバル化を進めたい石原氏と、国内雇用の減少を恐れた塩路氏は対立。しかし1984年、金銭と女性問題のスキャンダル記事が写真週刊誌に掲載された塩路氏は、社内での力を急速に失っていった。
当時を知る関係者によれば、この記事は人事部内の対策チームが仕掛けたもので、塩路氏に「労働貴族」のレッテルを貼り、地位の抹殺を図ったものだった。

































無料会員登録はこちら
ログインはこちら