「院が、どうしているかとおっしゃっておられますので、本日そちらに参ることにいたしました。ほんの少し外出するにつけても、あんな悲しみの中、よく今日まで生きながらえたものだと胸を搔きむしるような思いでございます。お目に掛かってご挨拶するとなおのこと悲しみがこみあげてきそうですので、そちらへはお伺いいたしません」
とあり、母宮は流す涙で目も見えないほど泣き、返事を書くこともできないでいる。左大臣がすぐに光君の元に来る。こらえきれないように袖を顔に押し当てて離すことができない。それを見ていた女房たちもさらに悲しくなるのだった。
この世のはかなさに思いめぐらせて、さまざまな感慨を覚えて泣く光君は、悲しみに深くとらわれていながらも優美でうつくしかった。左大臣はなんとか涙をこらえて口を開く。
「年をとりますと、ささいなことにも涙もろくなるものですが、ましてや涙の乾く間もないくらいのどうしようもない悲しみを、とても静めることができません。他人が見ても、取り乱して、心の弱い者だと思うでしょうから、私はとても参上などできません。何かのついでに、そのように奏上ください。余命幾ばくもない老いの果てに、子どもに先立たれるなんて、こんなにつらいことがありましょうか」
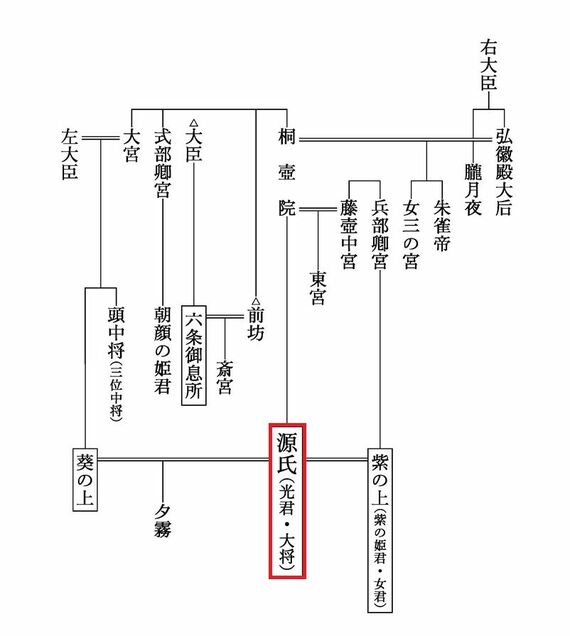
だれも彼も心細そうに
無理に気を静めて言う左大臣は気の毒なほど痛々しい。光君も洟(はな)をかみながら言う。
「死に後れたり先立ったりする命の定めなさは、この世の常と承知しているものの、いざ自分の身に降りかかってきますと、悲しみの深さは何ものにも比べられないものですね。院にも、この様子を奏上いたしましたら、おわかりになってくださいますよ」
「では、時雨もやみそうにありませんから、暮れないうちにお出かけなさいませ」と左大臣は光君を急かす。
あたりを見まわすと、几帳(きちょう)の陰や襖(ふすま)の向こう、開け放たれたところには、三十人ほどの女房たちが、濃い鈍色(にびいろ)や薄い鈍色の喪服をそれぞれに着て、だれも彼も心細そうに泣きながら集まっている。なんと悲しい景色だろうと光君は思う。































無料会員登録はこちら
ログインはこちら