木造は石造より命が長い?プロが語る建築の本質 東洋の「木の文化」と西洋の「石の文化」の違い
日本の伝統的な住居は、まさにそういうものでしょう。縁側があることで「内」と「外」が一体化しているので、外部が内部に入り込み、内部が外部に出ていくような構造になっています。そういう「空間」のあり方によって、自然との共生という価値観が表現されているわけです。
20年おきに社殿をつくり替える伊勢神宮の「式年遷宮」も、自然との共生を図る「木の文化」ならではの習慣です。材料は新調されているので、昔のまま遺跡として残っているわけではありませんが、消え去ってもいません。
昔から同じ技術を使って同じ姿形を保つことで、1300年前から変わらずに存在しています。このやり方が続くかぎり、その建築としての命は石造建築より長いかもしれません。
「木」と「石」二つの文化から見える西洋と東洋の違い
こうした「木の文化」に対して、西洋の「石の文化」は自然を人間に対する脅威と見なしています。自然という「外敵」から自分たちを守るためには、ちょっとやそっとでは壊れない頑丈な素材を使わなければなりません。
そういう自然観の背景には、気候風土の厳しさもあるのでしょう。とくにヨーロッパ北部は冬の寒さが過酷なので、日本の縁側みたいな開放的な構造にはできません。
城などを見ると、開口部が小さくなっています。そういったことも含めて、西洋では厳しい自然を抑え込むような構造が建築に求められました。
西洋では、キリスト教の影響で「人間中心主義」が広がったとも指摘されます。世界の中心にいるのは人間だから、自然はその人間によって支配されなければいけない。
そこが、人間を自然の一部と見なす東洋とは根本的に違うというわけです。そういうキリスト教的な考え方も、建築における「石の文化」から始まっていたのかもしれません。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

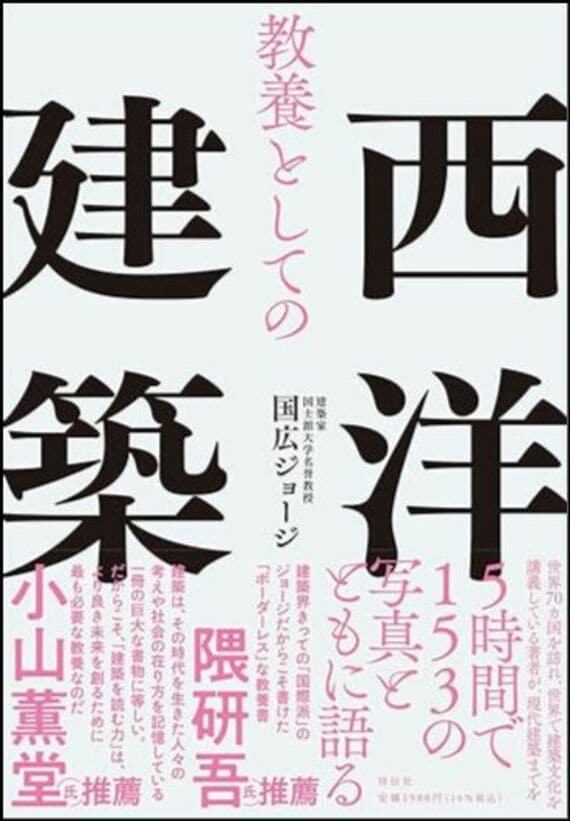































無料会員登録はこちら
ログインはこちら