やっと涙を抑え、光君はことの顚末を話す。
「本当に奇妙なことが起こったんだ。驚くのなんのって言葉にならないくらいのことだ。こんな非常時には読経をしてもらうのがいいらしいから、その手配をさせよう、願(がん)も立てさせようと、阿闍梨にも来てくれるよう頼んだのだけれど、どうなっている」
「それが、昨日比叡山(ひえいざん)に上ってしまったんです。それにしても、なんとも奇っ怪なことでございますな。姫君は、前からご気分がお悪いようなことはございましたか」惟光が問う。
「いや、そんなことはなかった」と答えて光君はまた泣き出す。その姿がじつにはかなげで痛々しく、惟光まで悲しくなって、おいおいと泣いた。
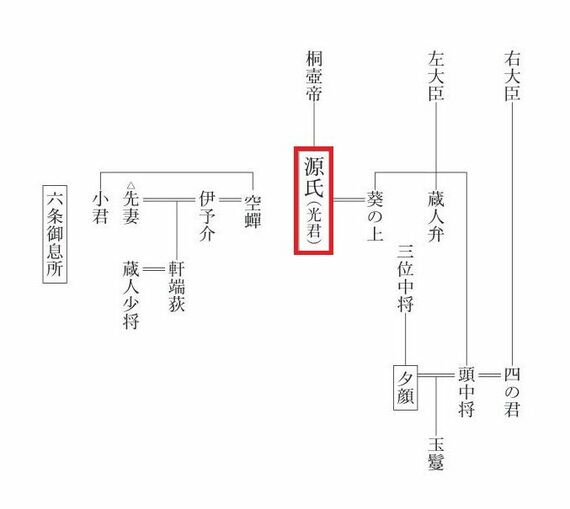
亡骸をひとけのないところへ
年齢を重ねて、世の中のあれこれに経験豊富な者ならば、こんな時には頼もしいのだろうが、光君も惟光もまだ年若く、どうしたらいいのかまるでわからない。それでも惟光は言った。
「ここの管理人に相談するのはまずいでしょう。管理人自身は信頼の置ける人だとしても、何かの折につい口をすべらせてしまうような身内がいないとも限りません。まずこの家を立ち退(の)きなさいませ」
「けれど、ここよりひとけのないところなんて、あるだろうか」
「それはごもっともです。女君が前に住んでいたあの宿では、女房たちが悲しみに暮れて泣きうろたえるでしょうし、隣近所が立てこんでいて、聞き耳を立てる者も多いでしょうからどうしても噂は広がりますよ。山寺なら、葬儀などは珍しくありませんから、目立たないのではないでしょうか」と、惟光はあれこれと考えをめぐらせる。「昔知っていた女が、東山で尼になっております。そのあたりに姫君をお移しいたしましょうか。私の父親の乳母(めのと)だった者ですが、すっかり老けこんでそこに住んでいるのです。そのあたりは人がよく行く場所ではありますが、ひっそりとしています」と言う。
すっかり夜が明ける前、管理人たちがそれぞれの仕事をはじめるざわめきに紛れて、車を寝殿につける。
光君は、亡骸(なきがら)を抱くことがとてもできそうもないので、昨夜共寝をした薄い敷物に彼女をくるみ、それを惟光が車に乗せる。女はひどく小柄で、死人という気味悪さもまるでなく、かわいらしい顔をしている。しっかり包めずに、敷物から髪がこぼれ出ている。光君の目は涙で見えず、どうしようもない悲しみに打ちひしがれて、せめて最後まで見届けようと思うものの、
「早く馬で二条院へお帰りになってくださいませ。人の往来が多くなりませんうちに、早く」
と惟光が急(せ)かす。惟光は、右近を亡骸に相乗りさせ、馬は光君に譲り、自分は歩きやすいよう指貫(さしぬき)の裾を膝まで上げて徒歩で行くことにする。まったく奇っ怪なできごとで、思いも寄らないような野辺(のべ)送りをすることになったものだ、と惟光は考えるが、光君の悲しみに沈んだ様子を見ると、死の穢(けが)れに触れようが、世間に何か言われようが、自分のことなどどうでもよくなるのだった。光君は何か考えることもできないまま、茫然自失の体で二条院に帰り着いた。

































無料会員登録はこちら
ログインはこちら