このオファーによって理研は、外形的には「4月以降も研究者として働く席を用意した」という形を作れる。もしも研究者側がこれを断れば、「雇い止めではなく、研究者が自らの意思で理研から出ていった」ということにされてしまう。
その一方で理研は、理事長特例によるAPの期間は最大で2年間(2024年度まで)、延長は不可とする制約を設ける。APの期間が終われば「もう事業は終了した」という理屈で雇用を打ち切ることを考えているようだ。期間の上限があるのはそのためだ。
AP終了後は雇い止めか
APは直訳すれば「任命事業」。理研は、APの契約書をつくるにあたり研究者に対し「研究の内容のテーマを詳細にまで絞ること」を強く求めているという。APに就いて理研に残る予定のある研究者は「理研は、とにかく研究範囲を狭く書かせようとしてきた」と証言する。
その理由は何か。APの期間の終了後に、無期雇用への転換申込権を持つ研究者が権利を行使しても「APの事業は終了し、設定した研究テーマの仕事は既になくなった」という理屈で理研から追い出すためなのではないか。有期雇用の研究者の中には、そうした不信感がある。
3月末で有期雇用が通算10年になる研究者は、4月以降に1日でも雇用されれば本来は無期雇用になれるはず。だが、理研はこうしたやり方で無期転換を実質的に無効化する可能性があるようだ。ここに、理研がAPを新設した仕掛けの意味がある。
実際、理研を訴えている研究者らは、訴訟の中で「APが終わった後も無期転換への申込権を行使すれば、理研で研究を続けられるのか」の説明を求めているが、理研は否定的だ。
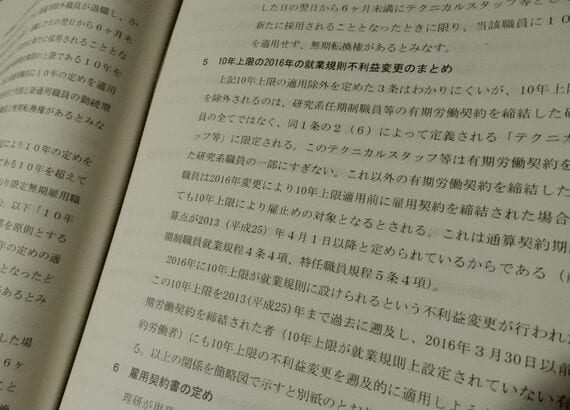
3月17日にさいたま地裁で開かれた口頭弁論で理研側の弁護士は「APは(それまでとは別物の)新たな雇用契約で、雇い止めの議論とは関係がない」と主張した。原告のひとりで、理事長特例によるAPのオファーを受けるB氏は「4月から研究ができなくなると困るのでAPの話を受けるつもりだが、2年間で雇用が終わる条件を了承したわけではない」と憤る。
現時点で理研を訴えている研究者らは5人にとどまっている。訴訟を起こせば、所属する研究室が理研から予算配分などで報復される恐れがあることや、今後の転職にも響くおそれがあるため、多くの人が「泣き寝入り」しているのが実情だ。
法廷ではたった数人の戦いだが、訴える研究者側も、理研側も譲る気配はない。後に続く者に影響するからだ。来年や再来年の春にも、理研が同じような雇い止めを行うかどうかは、この訴訟の行方が左右するところが大きい。
B氏は「先頭を切って戦う責任として、理研のやり方の違法性を明らかにし、無期雇用を勝ち取りたい」と話す。
東洋経済は理研に対し、一連の問題に関する見解を尋ねたが、回答はなかった。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら


































無料会員登録はこちら
ログインはこちら