翌年の2月であった。ある週刊誌が同書について、取材したいと申し入れてきた。指定された日は予定で詰まっていた松下は「この本についてお前がいちばんわかっていると思うから、自分に代わって取材を受けよ」と言う。先方に連絡すると、急いでいるのでそれでもいい、という返事。しかし、電話の話の内容から、批判記事にまとめようとしていることがわかった。とは言え、私は、大阪から急遽、東京の、その出版社に出向いた。
厳しい記者からの取材
予想通り、質問は厳しかった。私は、丁寧に時間をかけて、説明に説明を必死で続けた。予定の時間は越えて、もう23時近くになり、帰る最終の新幹線もとっくに過ぎていた。はじめは詰問調の記者も、私の必死の答える姿に、憐れと感じたのか、次第に穏和になり、それどころか、ホテルを探すことまで心配し、あちこちに電話をしてくれた。あいにく、雪が降っていた。ということもあるのか、どこのホテルも満室。ただ新宿の京王プラザが1室空いていた。
「宿泊料金が高いですが、いいですか」と、記者が気の毒そうに言うが、そこしかなければ仕方がない。そこに宿泊することにして、お礼を言いつつ、何回も頭を下げた。その翌朝、5時に起きて、いちばんの新幹線で大阪に戻り、そのまま、松下のところに報告に行った。
「詳細に説明してきました。お書きになったお気持ちも十分、話をしてきました。そういう松下さんの気持ちなのかと理解していただきました」と報告すると、「それでいい」と笑顔で応じてくれた。
しかし、その週刊誌が発売されて、見ると、『崩れゆく日本』については、比較的淡々とした内容紹介であったが、あろうことか、同書の内容を引用して、「松下電器批判」になっていた。驚いた。私は一言も触れていない内容に仰天した。松下に、そのことを話しながら、34歳であったが、心のなかで涙が溢れそうになった。
松下は、私の報告を、週刊誌を開き眺めながら、聞いてくれたが、聞き終わると、ニヤリと笑いながら、
「これ、きみが取材を受けてくれたんやな。一生懸命やっても、週刊誌の記者さんは、はじめからひとつの結論を持っているんや。仕方ないわ。こんなもんやで。きみ、心配せんでいいよ。まあ、辻斬りにあったようなもんや。いや、むしろ、この本のいい宣伝になっとるやないか。さらに売れるよ、この本は。きみがまた、貢献してくれたわけや」
その言葉に、感動をした。ありがたかった。ほんとうに涙が出そうになったことを今でも思い出す。
そして、呵々大笑して、一言。
「まあ、これからな、きみもいろいろ、こういうことを経験するようになる。けどね、辻斬りの刃をヒラリとかわす名人もいるわな。そういう、刃をかわす名人になれや。これから勉強していったらな、きみも名人達人になるわ」
ちなみに同書は、60万部を超えるベストセラーになり、昭和51年1月には、全国の書店が選ぶ、最も書店の売り上げに貢献した書として、第10回「新風賞」を受賞している。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

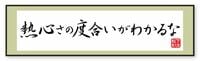
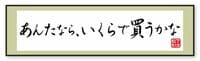
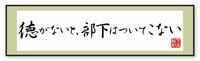
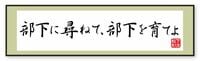




























無料会員登録はこちら
ログインはこちら