認知件数増いじめ問題解決に「協働」という視点 「構造化」のアプローチで問題の突破口を探る
安部:率直に、いまの日本ではいじめ問題は改善に向かっていると思いますか。
谷山大三郎:文部科学省のいじめ認知件数(教員や周囲がいじめに気づいた件数)は、2019年には過去最高の件数になりました。先生たちが積極的にいじめを見つけようとしていて、いじめへの意識が高くなっていることはあると思います。
暴力行為や重大行為などに関しても、隠蔽するのではなく積極的に見つけようとする動きは確実に出てきていると思いますね。
安部:先生たちも、いじめを把握できるようにはなってきたということですね。
谷山:そうですね。あとは「いじめの定義(※)」の共通認識が広くなり、子ども側の気持ちを考慮する定義になったことも大きいかもしれません。ただしこの定義は、よい部分もあれば、それゆえにひずみが生まれているところもあります。
たとえば、相手が「悲しい」「傷ついた」と感じれば、それはいじめになる。「授業中に算数の問題が解けず困っている子を見て、よかれと思って教えてあげたら、その子が悔しさから泣いてしまった」というケースも、いじめということになってしまうんです。
いじめの定義とは
先日、被害者の保護者の方と学校の校長先生、政治家の方、いじめ探偵の方と話し合う機会があったんのですが、そこでもいじめの定義に関する意見は分かれましたね。
「定義が広すぎると大事なことを見落としてしまう可能性がある」と考える人もいれば「定義が狭くなると、いじめなのにいじめと認定されないリスクがある」という意見もありました。
さらに、いじめを認知した場合、教員は三ヶ月間の経過観察をする必要があるんですね。教員の多忙化が問題になっているなか(※)、いじめの定義が広くなっていることで、すべてのケースに同じように経過観察ができるのかという点もあります。
※詳しくはリディラバジャーナルの「教員の多忙化」特集をご覧ください
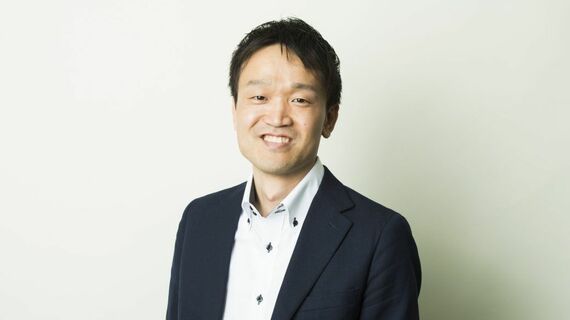
安部:いじめ問題を構造化するメリットは、どんなところにあると考えていますか。
































