はびこる不誠実対応「学校での事故」の悲痛な実態 「真実を知りたい」と願う当事者たちの闘い
文科省の報告書は、伶那さんの死がそもそも健康に問題があったとにおわせるようなものではないか。伶那さんに既往症はなかった。松田さんはあのときの憤りを忘れない。
「まるで私が(既往症を)隠していたかのようですよね。これを見たとき、頭が真っ白でした。血がにじむような思いをして話し合いを重ねてきたことが、何だったんだろうって。わかりあえていると思ったんですけど……。両担任の先生は心を尽くしてやってくださったって思っていますが、ひとたび、『学校』になってしまうと、こうなっちゃうんですよね」
現場の教諭と管理職との認識の差。それを感じずにはいられなかった。
「事故が起きたとき、何があったのか知りたいというのがいちばんなので、そこをきちんと開示してほしいと思います。全部提示して終わりじゃなくて、きちんと調査検証していかないと無駄になるし、因果関係を調べないと問題があったのかなかったのかも言えない。(それなしに)学校は何も言える立場にはないと思います」
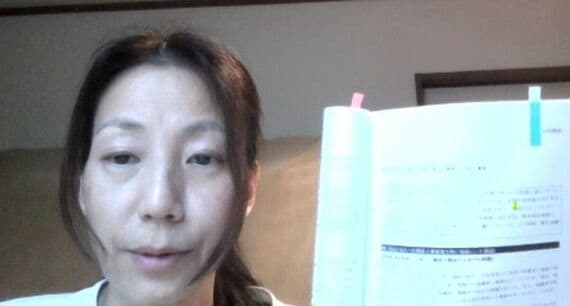
子どもに障害が残ったケースも
さらに別の例を紹介しよう。事故で子どもに障害が残り、訴訟に発展したケースだ。
福岡県久留米市の河村和美さん(55)の次男・啓太さん(23)は、市内の特別支援学校中等部3年だった2012年9月、給食をのどに詰まらせ窒息し、重い脳障害が残った。啓太さんは1歳のころ、脳性まひと診断され、身体障害者1級の認定を受けていたが、事故前は表情豊かに意思疎通ができたほか、車いすで通学もできていたという。
それなのに、事故によって両目を失明し、聴力を失った。呼吸のために気管切開し、胃ろうで栄養を取るようにもなる。河村さんは、寝たきりになった啓太さんに24時間付き添い、介護している。
事故の日。河村さんは、学校からの連絡で搬送先の病院へ駆けつけた。啓太さんは一命を取り留めたものの、心肺停止が30分ほど続いたという。病院で待機する教諭は泣いている。その姿を見て、責める気持ちにはなれなかった。その後、容体は変わらないことを徐々に感じ、後遺障害の重さを認識したという。































無料会員登録はこちら
ログインはこちら