都道府県単位で異なる健康保険料率に注意 あなたにも出来る!社労士合格体験記(第79回)
社労士試験の過去問題に「健康保険制度は、長年にわたり健康保険組合が管理運営する組合管掌健康保険と政府が管理運営する政府管掌健康保険(政管健保)に分かれていた。しかし、平成8年可決成立した健康保険法等の一部を改正する法律により、平成10年からは、後者は国とは切り離された全国健康保険協会が保険者となり、都道府県単位の財政運営を基本とすることになった」という間違った選択肢が出題されたことがあります。
正しくは「平成18年」に可決成立した健康保険法等の一部を改正する法律により、「平成20年(10月)からは」ということになります。年や月の数字を引っかける問題は、社労士試験の頻出なので注意してください。
全国平均を決めてから都道府県単位を決定
上記選択肢の「国とは切り離された全国健康保険協会が保険者となり、都道府県単位の財政運営を基本とすることになった」という正しい記述部分も重要です。
協会けんぽの本部(主たる事務所)は東京にあります。協会の役員は、理事長1人、理事6人以内および監事2人で構成され、運営委員会が置かれています。運営委員会の委員は9人以内(事業主代表、被保険者代表、学識経験者代表それぞれ同数)で厚生労働大臣が任命し、任期は2年です。一方、支部は都道府県単位で、支部ごとに評議会が置かれています。
都道府県単位という影響が最も顕著なのは保険料です。まず、一般保険料率は法律では1000分の30から1000分の120までの範囲(3%から12%)と規定されていますが、今年度(平成26年度)の全国平均は1000分の100(10%)で、これを労使折半で払います。
特徴的なのは全国平均を先に決めてから、都道府県単位保険料率が決定されることです。2013年度で見ると、最も高いのは佐賀県の10.16%、最も低いのは長野県の9.85%、ちなみに東京都は9.97%です。なお、40歳から64歳までの方々(介護保険第2号被保険者)は、これに全国一律の介護保険料率1.55%が加わります。また余談ですが、協会けんぽの東京支部は最近、わが地元・中野区のセントラルパークに引っ越してきました(なお、平成26年度の介護保険料率は1.72%に引き上げられました)。
次回は、九州博多での再会です。
(撮影:梅谷秀司)
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら



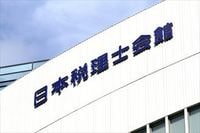



























無料会員登録はこちら
ログインはこちら