人を死に追い込む「ことば」と感染症の怖い共通点 ノーベル賞作家・カミュの「ペスト」を読み解く
カミュは、その紡ぐ「ことば」が、論説やエッセイであろうと、彼自身の偉大な文学作品と同じ労力を注ぐことをいとわなかった。「ことば」こそ、自分が拠って立つ場所であることを知っていたからだ。
「りっぱな人間、つまりほとんど誰にも病毒を感染させない人間とは、できるだけ気をゆるめない人間のことだ。しかも、そのためには、それこそよっぽどの意志と緊張をもって、決して気をゆるめないようにしていなければなら」なかったのだ。
カミュは、あらん限りの力と繊細さをこめ、新聞「コンバ」を中心にして、論説を書いた。社会や公共へと受け渡す「ことば」にも、文学と同じ労力をさいて。けれども、社会は、カミュの「ことば」を拒んだ。
左派にも右派にも属さず、あるかもしれない「真実」を目指して刊行されていた新聞「コンバ」は、党派色の濃い、旗幟鮮明な左右の新聞に読者を奪われていった。
1947年6月3日、カミュは「コンバ」に最後の社説を掲載し、編集長を辞職することを公表した。『ペスト』の刊行は、その10日後のことだ。
カミュの代表作「異邦人」は自分自身
カミュは、国籍を問われたとき、こう答えた。
「ええ、ぼくには祖国があります。それはフランス語です」
カミュの名を世界に知らしめたのは、デビュー作『異邦人』だった。主人公ムルソーは、どこにいても、自分が「異邦人」であると感じる。どんな国家にも、どんな民族にも、所属できない。どんなイデオロギーや倫理や慣習にも服従することができない。どんな正義も、それが「正義」であるだけで、彼は、従うことができないと感じるのである。
そんなムルソー=カミュが、唯一、生きることが可能だったのは、その作品の中、フランス語という「ことば」が作り出した束の間の空間だった。その空間だけが、彼を「等身大」の人間として生きさせることができた。
フランス語という「ことば」が作り出した、束の間の、「文学」という空間。「文学」はあらゆるものでありうるが、自らが「正義」であるとは決して主張しないのである。「ことば」は人を殺すことができる。だが、そんな「ことば」と戦うことができるのは、やはり「ことば」だけなのだ。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

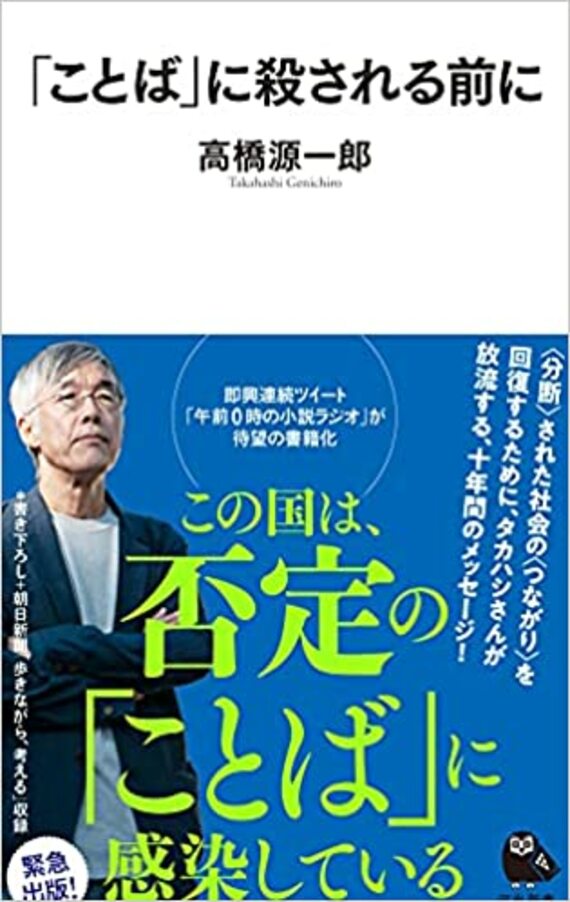






























無料会員登録はこちら
ログインはこちら