
患者のさまざまな「痛み」を和らげる
――「緩和ケア」とはどんな分野、内容でしょうか。言葉そのものは耳にする機会も増えてきたように思いますが。
病気で身体の苦痛が生じたり、こういうふうになったのはどうしてだろうと落ち込んだり。人には普通にあることですね? そうしたさまざまな「痛み」を和らげていくのが緩和ケアの一番大きな目的です。日本では、がんの領域で発展してきました。
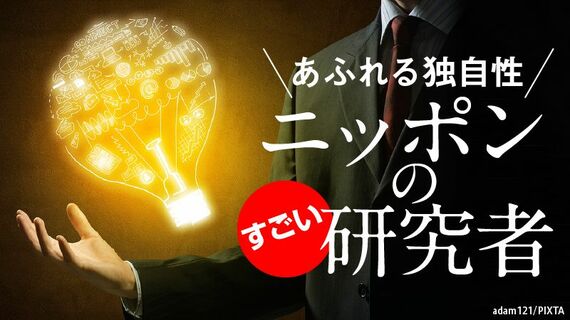
がんは、診断されたときから緩和ケアが始まります。治療と並行して緩和ケアを行うわけですね。特に2006年にがん対策基本法ができてからはそうなりました。基本法以前は、緩和ケアには「終末期看護(ターミナルケア)」の意味合いが強かった。
今は違います。がんと過ごすすべての日々で生じるさまざまな苦痛を緩和していくこと、それにより、患者のQOL(Quality of Life、生活の質)をより良くしていくとことが大きな目標です。もちろん、ターミナルケアの役割も含みながら、ですが。
――スピリチュアルケアへの関心をいつから持っていたのでしょう?
1995年ごろから、スピリチュアルケアを研究しています。当時はホスピスで働いていました。日本にはまだ2カ所ぐらいしかない時代です。その間、英国に短期間勉強に行く機会があり、現地で看護師さんたちが自律性をもってケアしている姿を見た。それがきっかけですね。
臨床の場で働いていると、患者さんたちの声を聞くわけです。「悪いことなんてしてないのにどうしてこんな病気になったんだろう」とか、「家族に迷惑をかけるだけだから早く終わりにしたい」とか。日常茶飯事です。

































無料会員登録はこちら
ログインはこちら