孤独死を弔い続ける神主が危ぶむ「強烈な孤立」 事故物件の「お祓い」に映る無縁社会の哀傷
「生命って本当はとてつもなく重い。それが今の日本では感じられない。尊厳が与えられるのは、ごく一部の裕福な人たちだけ。
日本は戦後、経済的には復興したけど、精神的には疲弊しちゃったんだと思う。『うちのアパートで店子さんが亡くなってかわいそうだったね』と、その発想がない。起こったことが嫌で迷惑なだけ。昔は大家さんとはうっとうしいほど人間的な付き合いがあったわけだ。今は、ただ家賃だけ払えばいいという考え方。本当に日本人は冷たくなった」
そう語る金子の背中は少し寂しそうだった。しかし、数々の現場と向き合ってきた金子の歯に衣着せぬ言葉は、ズシズシと私の心に突き刺さり何よりも重かった。
誰もが忌避する人の最期──、そんな日本社会の現実と向き合う男の葛藤が、まさにそこにあった。しかし、どんなに現場で吐き気がしても、周囲の人に心ない言葉を投げつけられても、それでも、金子宮司はこの仕事が好きだという。その原動力とはなんなのだろうか。
俺が最後の砦
「だって亡くなった人にとっては、俺が最後の砦。自分で言うのもおかしいけど。その人に、『これまでの人生、大変だったね』と言えるのは俺しかいない。現場で式典が始まると、汚いという感覚とか、臭いとか一気に消える。孤独死する人は葬式もやらないことも多い。だから自分だけは『お疲れさま』と言って死者と初めて、対話をする。神主がきてお祓いをした。それで、この物件に入ろうかなと思う人がいる。そんな宗教者としての役割が社会にあるなら、俺としてはそれでいい」
そこには故人を思う金子の優しさがあった。そして、神主として少しでも世の中に貢献したいという使命感もある。それはどんな形であってもいい──金子はそう考えている。
事故物件が忌避されるのは確かだ。不動産会社はお祓いしたという安心が欲しい。増え続ける孤独死のお祓い需要は、お飾りの神事というアリバイ作りと化しているのが偽らざる現実だ。しかし、たとえそうであっても、宗教者として社会に必要とされるなら、それはそれでいい。そして、金子にはそんな社会と真摯に向き合おうとする懐の深さがあった。私は無縁社会から目を背けずに向き合うそんな稀有な宗教者の姿こそが、この社会の光明で、希望なのかもしれないと思った。
神社の鳥居が夕日に照らされて赤く、まぶしくあたたかな光を帯びている。明日も金子は早朝から壮絶な孤独死物件に車を走らせる──。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

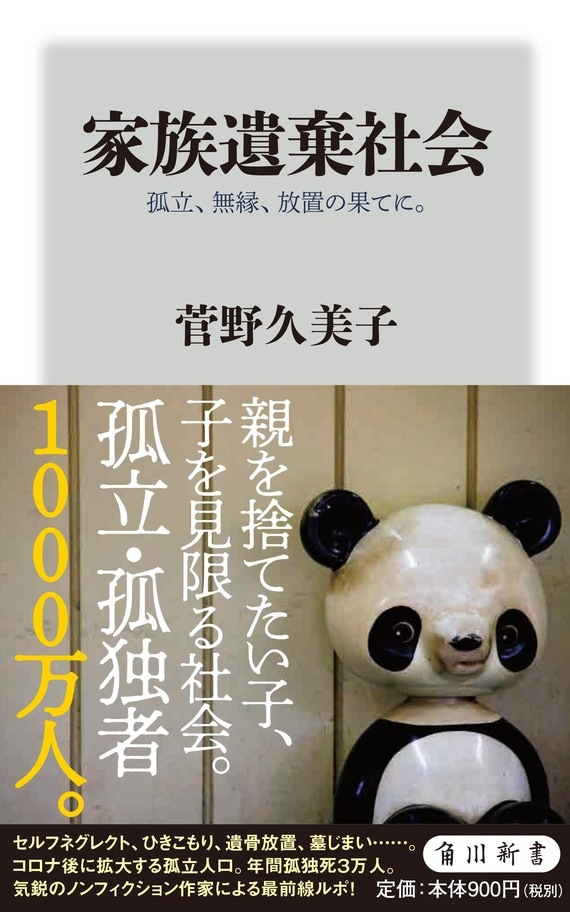






























無料会員登録はこちら
ログインはこちら