片や、会社というコミュニティーに帰属感、居場所感を持っている人々ほど、前述のように少しずつ「自分が何者なのか」という感覚があやふやになっていく。頭では〇〇会社の社員であるということを理解はしているものの、確固たるリアリティーが伴いづらくなるのだ。そして、人によっては自分のやっている仕事の価値が揺らぎ始め、「この仕事にどれほどの意味があるのか」といった疑念が生じるかもしれない。
とりわけ社員のロイヤルティー(忠誠心)の維持を「場所性と直接性」というアドバンテージに頼ってきた企業ほど、このような社員に底流する根源的な問いに答えることが恐ろしく困難になってしまう。よくも悪くも「身体的な近接性」、非言語(ノンバーバル)コミュニケーションによる化学反応を重んじてきたからだ。「その場の空気」だけが作り出せる「らしさ」の落とし穴である。
「『自分自身を何かに同一化(アイデンティファイ)すること』、は自分でコントロールもできなければ、影響も及ぼせない未知の運命に人質を差し出すことを意味する」と述べたのは、社会学者のジグムント・バウマンであった(『アイデンティティー』伊藤茂訳、日本経済評論社)。
会社=コミュニティー的な組織体としての性格
会社への帰属意識をベースにした「社会的なアイデンティティー」の占める割合が高い人々ほど、バウマンの言う「未知の運命」に身を委ねざるをえない状況に直面する恐れが増すのだ。一見、会社へのロイヤルティーが低い社員であったとしても、そこでの人間関係で多少なりとも「承認不足」を補っている場合、どうしても物理的な会社という「場」で自尊感情を得る必要性に迫られる。
日本では依然として会社=コミュニティー的な組織体としての性格が根強い。それによる同調圧力と過剰適応がワーカホリックの主な原因にもなっている。バウマンは、安定や不安の解消の代替案として、あるコミュニティーが魅力的に映ったとしても、確固たる忠誠を要求する門戸の狭い「自己同一的なコミュニティは、逆に悪夢、つまり、地獄や監獄のヴィジョン」(前掲書)だと極言する。要は、どこかに「安住の地」があるという幻想から解き放たれなければ、最悪の場合「会社と心中」することを示唆している。
もちろん、会社以外の多様なコミュニティーと接点があれば、このようなある種の〝コップの中の嵐〟〝から騒ぎ〟とは無縁でありうる。

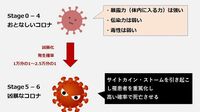





























無料会員登録はこちら
ログインはこちら