事態を重く見た農林水産省は、技能実習生をあてにしていた農家や法人を対象に、支援策に乗り出している。
新しく募集をかけて確保した代わりの人材に対して、当初の予定の賃金を上回った場合には、1時間500円を上限に国が補助する。交通費や宿泊費、保険料から、農家やJAなどによる人材募集サイトへの情報の掲載や、チラシ作成の費用も補助の対象とする。しかも、JAの職員が援農をした場合には、1日4000円程度を上限に支援するという。
この「農業労働力確保緊急支援事業」に、農水省は46億4600万円を2020年度補正予算案に計上している。その上、それまで禁じられていた技能実習生の転職を可能にするなどして、農業就労者を国内で補う方針だが、それでも人材が確保できるとは限らない。各地で作付けの見直しも行われている。生産性が低下する可能性は高い。
仮に、この”コロナ・ショック”で、都市部での職を失った日本人が農業従事者となっていくことが増えるのだとしたら、それは終戦後の状況に重なる。
焦土と化した祖国に復員した人々が、折からの農地解放も手伝って、農業をはじめる。食料の増産は進み1960年には自給率は80%までになった。しかし、それも同年に更改された日米新安全保障条約によって、アメリカからの穀物輸入が増えると、自給率は低下の一途をたどり、いまや38%になっている。
その間の1973年には、当時のニクソン大統領が大豆の国内価格の高騰から緊急輸出停止措置をとったことがあった。既にアメリカに大豆の輸入を依存していた日本は、味噌や醤油がなくなる、豆腐が食えなくなると、大騒ぎになった。
食料をめぐる世界的な争いの可能性
中国から感染拡大がはじまった新型コロナウイルスだが、各国は都市封鎖し、人の流れを止めた。日本は、中国からタマネギやニンジン、ニンニクなどの野菜を加工したものを多く輸入している。その供給が急減している。国内の混乱から、サプライチェーンをもとに戻すにも時間がかかる。
先行きの不透明な新型コロナウイルスによる地球規模の侵略。自国ファーストに立てば、どこで食料供給が停まるか、わからない。
このままいけば100年前の第1次世界大戦後からやがて訪れる世界恐慌といっしょに、自国利益優先のブロック経済圏を確保していったように、食料争奪をめぐる戦争へと進んでいく可能性はある。
その前に、国土と食の安全保障を考えてみる必要があるだろう。新型コロナウイルスは、世界のパラダイムを組み換えてしまう可能性を秘めている。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

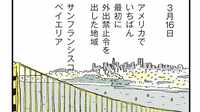





























無料会員登録はこちら
ログインはこちら