飲食店等の経営が大幅に悪化してしまった場合には、店を閉店し、賃貸借契約を解除することで賃料の出費を抑えたいというところもあるだろう。飲食店が営業自粛をしているという状況で、賃借人のほうから契約を解除することができるのかどうかである。
これもまずは契約書の条項を確認することから始まる。そして、それに当てはまらない場合には、民法の規定に従って解除できるかどうかを考えていくことになる。その場合の問題は、賃貸人の側に債務不履行があったのかどうか、つまり、賃貸人の主要な義務である賃貸スペースの提供が行われていたのかどうかである。
今のように休業要請を受けて飲食店が自主判断として休業するという形を取る限り、賃貸人の側には何の責任もない。飲食店が賃貸しているスペースが商業施設の中にあり、その商業施設が2週間や1カ月閉鎖となった場合にはじめて賃貸人の側の責任となるであろう。
従って、解除ができるケースは、かなり限られてくる。通常のビルの1階に入っている飲食店の場合には、賃貸スペースは継続的に提供されているので、賃貸人の側に責任はなく、解除を行うことはできないという結論になる。
飲食店はどうすればよいのか
上記に見てきた通り、残念ながら、法律的に飲食店が抱える新型コロナ対応問題を解決することは難しい。となると、賃貸人との話し合いで解決の方向性を見つけるしかない。飲食店側は、賃貸人は強い立場にあるから、自分たちの要望を聞き入れてもらえないと思っているところが多いと思うが、実はそうではない。
賃貸人の側も杓子定規の対応ばかりしていると、テナントとして入っていた飲食店が出て行ってしまい賃料が入らなくなる。歯抜け状態の賃貸ビルとなれば、次の賃借人も入ってこなくなる。
資金繰りに行き詰まり破産するところも出てくれば、賃料が入ってこなくなるばかりか、貸したスペースの原状復帰もしてもらえなくなる。そして、その費用は賃貸人の大きな負担(特に飲食店の場合には原状復帰費用は高額である)となる。
こうした状況であるから、飲食店から申し入れることで、賃貸人も対応をしてくれるはずだ。飲食店は、賃貸人に対して早くアクションを起こすことが必要である。
4月28日に野党が提出している家賃支払い猶予法案では、前年比で1カ月当たり20%以上減収となった中小の事業者などを対象に、政府系金融機関が代わりに家賃を返済したうえで、支払いを猶予するという。賃貸人や賃借人だけの問題にとどまらず、政府からの迅速な支援も求められている。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

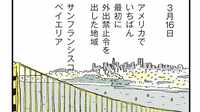






























無料会員登録はこちら
ログインはこちら