闘病中は親族でも面会できず、仮に容態が急変して亡くなってしまうと、最期のお別れをすることもほとんど不可能だ。死後はウイルスを封じ込める「非透過性納体袋」に入れられ、すぐに病院から火葬場へと搬送されることが多い。つまり、最悪の場合、「隔離されたまま死を迎える」のである。
隔離の恐怖は、アルベール・カミュが『ペスト』(宮崎嶺雄訳、新潮文庫)において「追放の状態」「追放感」と呼んだものに近い。患者本人だけでなく残された家族も、同じく針のむしろに座る気持ちにさいなまれる。
一方で、一方で、症状が回復して退院した人々は、一般社会に戻れるという本来喜ぶべき局面なのであるが、まだウイルスを持っているかもしれない要注意人物、「元感染者」といった視点から差別的に取り扱われることが少なくない。
感染者が回復後に再び陽性と診断される例は、実際に日本や海外で報告されている。身体に残存しているウイルスが再活性化したのか、再感染によるものなのかはよくわかっていない。未知のウイルスであることから、症状が治まった後もどのような経過を辿るのか、まだ不明な点があり疑念は簡単には拭えない。現行では、2回のPCR検査で陰性が確認されて退院するが、患者本人もしばらくは誰かを感染させることに脅え、家族や周囲の者も「再陽性」の可能性に脅えることとなる。
感染リスクゼロは自他すべての社会活動をゼロに
わたしたちにとって「感染リスク」がゼロであることは理想だが、それは自他のすべての社会活動をゼロにすることに等しい。ソーシャルディスタンシング(社会的距離)戦略は、その葛藤に対する当座の次善策といえる。さすがに「ゼロリスク」を追求すれば社会システムそのものが崩壊するからだ。「感染者叩き」「クラスター叩き」は、このような「ゼロリスク」(感染の危険性をゼロにする)志向と結び付くと非常に厄介だ。「ゼロリスク」に基づく「ゼロトレランス」(非寛容)の風潮へと早変わりするからである。
このゼロ=ゼロ思考が真に恐ろしいのは、「感染者でなくなった者を感染者とみなし続けること」、要するに他者の目から見て清浄化されず、いつまでも差別的なカテゴリーに固定化する可能性がありうるからだ。むしろ、特定の人物や集団を徹底的に攻撃して排除することによって、「自分だけはいつまでも安全地帯にいられる」とさえ思い始めるかもしれない。
前出の著書でソンタグは、「この世に生まれた者は健康な人々の王国と病める人々の王国と、その両方の住民となる」と語り、さらにこう続けている。
「人は誰しもよい方のパスポートだけを使いたいと願うが、早晩、少なくとも或る期間は、好ましからざる王国の住民として登録せざるを得なくなるものである」
わたしたちもこののっぴきならない現実を厳粛に受け止めた上で、現代において未曾有の事態を招来したウイルスと根気強く付き合う覚悟が必要だ。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら



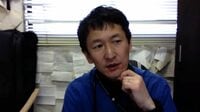






























無料会員登録はこちら
ログインはこちら