それでは、挑戦し、成果を収めた人たちは、その先にはどういう行動をとるべきか、です。
④ ほかのライバルを潰すのではなく、彼らから徹底的に学ぶ
福岡市には「ふくや」という有名企業があります。『福岡市が地方最強の都市になった理由』でも取り上げましたが、ふくやは、創業者と2代目社長という親子2世代で、2つの画期的開発をし、明太子を福岡の地域産業へと育てることにつなげました。
1つは、辛子明太子を開発し、そのノウハウをなんと無料で他企業に提供、結果として最盛期は1500億円を超える明太子市場を作り上げました。さらに、ふくやは九州でも他社に先駆けてコンピュータを用い、正社員も雇用するコールセンター要員を抱える画期的な通販システムを開発。これもまた他社に公開したことにより、キューサイ、やずやなどを含めてさまざまな九州の通販企業が参考にしたと言われます。
その結果、現在では九州は「通販大国」と言われるほど通販企業の一大集積地になっています。さらに、ふくやは地元の伝統行事である博多祇園山笠などにも多大なる貢献をし、最近では若者たちの企画などへの協賛も惜しまずしています。創業者の川原俊夫氏(1913-1980)は節税などは一切考えずに、納税するものはそのまま納税し、残ったお金はできるだけまちのために投資しつづけたことでも有名です。
「ネアカな地域」に人は集まる
このように、ねたみを持たれることがあっても、それ以上に感謝する人がでてきてしまうような工夫もあり、圧倒的な貢献度でそれを乗り越えてしまう人もいます。
成功者を潰すのではなく、成功者を讃え、教えを請い、そして褒められた成功者もオープンな姿勢で対応する。このような連携が発揮されたとき、地域に競争力のある大きな産業が生まれます。
ジメジメと潰し合いをする地域よりも、当然ながらネアカで笑って飲んで楽しくやっている地域のほうに人は集まり、挑戦は成果を生み出し、その成果が潰されることなく、むしろ地域全体へと波及していくということも可能になるのです。
ねたみは、多くの人の心に住んでいるものです。だからこそ意識して、具体的な応援につなげたり、学ぶ姿勢に持っていくのもまた、気の持ちよう1つで大きく変わるのです。地域を変えることは、大層大げさな話を考えたり、補助金のことを考える前に、そんな自分1人でもできる、毎日の過ごし方を変えることから始まるのだと思っています。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

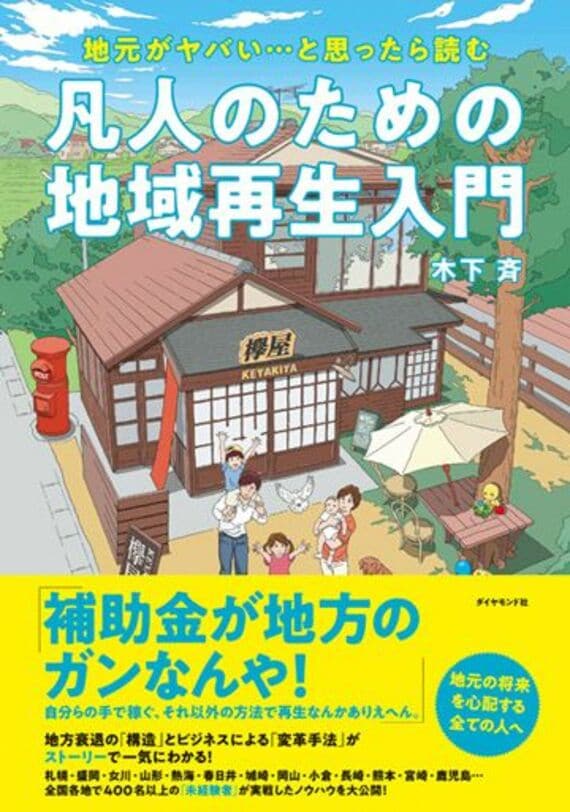
































無料会員登録はこちら
ログインはこちら