大災害で大きな経済的損失があったと感じられるにも関わらず、こうした統計にはほとんど影響が見られなかったり、むしろプラスに働いてしまうのは、これらが、毎年の生産活動というフローを表しているからだ。
大きな自然災害が経済に与える影響は、生産活動というフローと、その蓄積の結果、日本経済が保有している社会資本や生産設備、住宅などの資産というストックでは、大きく異なる。結論から言えば、大災害の経済的な打撃は主にストックの損失という形で現れる。失われたストックを再構築するために多くの生産が必要になるので、経済活動は活発化し、経済フローの指標であるGDPはむしろ高まることもあるというわけだ。
内閣府が公表している「国民経済計算」で多くの人が注目するのは、GDPをはじめとした諸数値が載っている「フロー編」と呼ばれる部分であろう。
国民経済計算には、あまり注目されることはないがストック編がある。フローである投資と資本ストックの間には、以下の式のような関係がある。

大災害による道路などの社会資本や工場などの民間資本の損失額は、ストック編の「期末(期首)貸借対照表勘定」の「その他の資産量変動勘定」に記録されている。
ここには「災害等による壊滅的損失」として、1995年にマイナス5兆9890億円、2011年にマイナス9兆5499億円、2016年にマイナス3201億円が計上されており、それぞれ阪神・淡路大震災、東日本大震災、熊本地震の被害とみられる。
ケインズの「穴を掘る」は非常事態の手段だ
報道でよく見かける「○○の経済効果」という試算では、多くの場合、売り上げや生産が何億円増えるかというフローの数字に注目している。こうした考え方を大災害に使うと、被災地の支援や復旧・復興のための各種事業活動によって売り上げが増えるので、経済効果はプラスになるというおかしな結論になってしまう。しかし、多くのストックが失われているという影響はきちんと統計に反映されており、これを勘案すれば経済的にプラスにはなっていない。
三面等価の原理から、「生産=支出=所得」なので、フローの生産が増えて所得が増えると経済的にプラスのように思えるが、これも大きな誤解だ。所得は増えているのだが、所得の増加分はすべて災害で受けた被害を解消するために使われてしまっている。仮に復旧事業の結果、完全に災害前の状態に戻すことができたとしても、災害が起こる前後を比べれば、多くの人が汗水流して働いた結果として何も新しく得たものはない。大災害によるGDPの増加は「タダ働き」を記録したものにすぎないのだ。
ケインズの一般理論の中に出てくる有名な「穴を掘って埋めるようなムダな需要に意味がある」というたとえ話は、大恐慌への対応としてこの本が書かれたことを念頭に置いて解釈する必要がある。ケインズ自身が「住宅の類を建設するほうがずっと賢明だが、何もしないよりはましだ」と述べているように、大恐慌で経済活動がスパイラル的に悪化するのを止めるためには、何もしないよりはムダな投資活動でも需要を作り出すことに意味があるという非常事態の手段として述べたものである。
災害がおこれば多くの人命が失われ、被災した人々の生活の困難といった金額に換算できない損失も非常に大きい。災害で経済にプラスがもたらされることはないのである。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

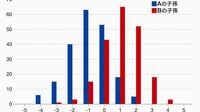


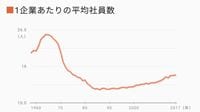


























無料会員登録はこちら
ログインはこちら