国策でグローバル人材を育成するという矛盾 古典を学ぶことが「エリートの反逆」を防ぐ
施:その点、西欧では古典を学ぶことが、自国の文化への帰属意識を育むことにつながっているのではないでしょうか。古典を学ぶことを通じて自らの文化的アイデンティティを意識し、「私も伝統の恩恵を被っているのだから、いずれそれに対して寄与していかなければ」と考えるようになる。藤本さんの言う「エリートの反逆」を防止する機能を、古典が担っているのではないかと感じます。
佐藤:今はどうかわかりませんが、少し前までヨーロッパのエリートは、ギリシャ・ローマの古典教養と密接なつながりを保っていた。皮膚感覚があるというか、日々の人生と重なり合うものとして位置づけていたのです。
たとえば20世紀前半のフランスの外交官で、すばらしい劇作家でもあったジャン・ジロドゥなど、「銀の時代」(白銀期)のラテン語散文に影響されたと語りました。ラテン文学の白銀期って、紀元1世紀から2世紀ぐらいですよ。それを手本にして、フランス語の文章を書いていると来るんです。この調子だから、1930年代の欧州情勢をテーマにした芝居を書くときも、ギリシャ神話に出てくるトロイ戦争をモチーフにしています。
大学自身が自らの役割を忘れている
施:私が日本の大学のあるべき姿と考えるのも、輸入学問を翻訳して伝えるだけでなく、日本の生活や伝統に根ざした叡智を集めて蓄え、それを体系化して後世に伝えていくことなんです。
でも今のように任期つきの教員ばかりになって、「論文は英語で書いて、英語のジャーナルに載せてもらって大学の国際ランキングを上げろ」という話になると、そうした国学的なものは育ちようがない。業績にならないので、任期切れで追い出されてしまいかねません。
藤本:アメリカの政治哲学者アラン・ブルームは「大学は社会に出て学べることを学ぶ場ではない。社会に出ても学べないことを学ぶ場なのだ」と述べています。市民社会の価値観とは違う価値観を持つ場だからこそ、同時代の市民社会を相対化して、批判的な視点を提供することができる。それが大学の社会に対する貢献のしかたであって、「社会で即戦力として働ける人材を供給しろ」と大学に求めることは違うということですね。大学自身がそうした自らの役割を忘れて改革に翻弄されている、ということが、最も大きな問題です。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

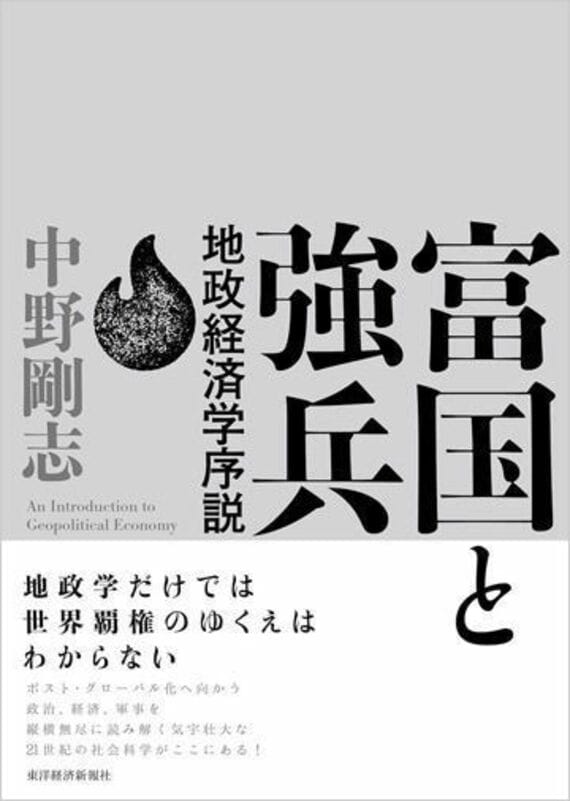






























無料会員登録はこちら
ログインはこちら