いまの資本主義が生む「錯綜する欲望」とは? NHK異色の「経済」番組が問いかけたこと
そこには両義性がつきまとう。「自由」な市場の可能性と、「野放図」な取引のジレンマ。「自由」と「野放図」、それを誰が倫理的にジャッジするのか?
人間の感情や人間そのものが「商品」として取引されることに、私たちは本能的な違和感を覚える。一方、自由なはずの市場取引で過度に「倫理」を強要することは、社会全体でマイナスの効果を生むこともありうる。このジレンマを、どう解けばいいのだろうか。
「交換価値」こそが重要という「錯覚」
そのためのヒントになるのが、アダム・スミス以来の「使用価値」と「交換価値」という概念だ。
「使用価値」とは、そのモノを使ったときの価値。先のリンゴの例で言えば「味」に相当する。一方の「交換価値」は、それが市場でいくらで取引されるかだ。リンゴの「売値」がこれにあたる。
無形のサービスも、需要と供給のマッチング次第、取引が成立すれば、どんな形でも問題はないのが、市場の原則だ。「ある時間、ある空間を過ごすことでの満足度」=「感情」もまた、需給がマッチングすれば「商品」となる。
その時、一次産業、二次産業のように、生産物の「使用価値」が見えやすく、その価値も価格も合意しやすい「物」の売買とは異なる状況が生まれる。
たとえば人気のコンサート。数十万の価値を見いだす人もいれば、まったく関心がない人には価値そのものが生じない。ゼロ円だ。いわゆる「感動体験」という商品は、その価格の決定が、主観的な価値観に大きく依存する。
そして、主観的な価値観によって生み出された一時的な高揚感、熱狂、カタルシスなどが商品となって、その主観的な価値を高めていくほどに、市場での交換価値も吊り上がり、交換価値の上昇そのものが体験の満足感を高め、主観的な価値を高めるという倒錯を生じさせる。ポスト工業化社会で広がる主力商品は、まさに欲望が欲望を増幅させ、「言い値」となる。
つまり、「使用価値」ではなく「交換価値」で、その本質的な価値が決まるという錯覚が生まれるというわけだ。そしてそれは、実際、錯覚などではなく、ポスト産業資本主義のシステムにあっては日常的な現象だと言えるだろう。

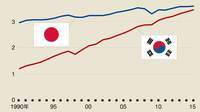































無料会員登録はこちら
ログインはこちら