社会科学に比べれば自然科学のほうが平均値を受け入れたのは早かったが、それでも最初は大きな抵抗があったようで、18世紀の科学者たちは平均という考えを拒否していたという(注1)。実験で得られた結果が理論から予測される値とずれるのは実験がうまくいかなかったからで、「最も信頼性の高い推定値として、最良の一つの観測値をとることが普及して」いた。
1人の研究者の複数の実験結果はもちろん、異なる研究者の実験結果を集めて平均値を取るということは、まったく別のものの合計値を計算するような意味のないことだと考えられていたらしい。おそらく、理想的な条件で実験を行えば結果は理論が予測する真の値になるはずだという考え方であったのだろう。
社会科学に平均という考えを持ち込んだのは、近代統計学の父とも呼ばれる、ベルギーの統計学者、ランベール=アドルフ=ジャック・ケトレーだ。多くの人の平均的な属性を持つ「平均人」という概念を打ち出したことで、平均の概念が急速に受け入れられたという(注2)。
19世紀前半の欧州では、紙に書かれた大量のデータが生まれて「第1次ビッグデータの波」が押し寄せていた。当時の人々はこれらの大量の雑多な数字をどう解釈すればよいのかわからなかったが、この問題を解決したのが平均という考え方で、20世紀の初め頃には社会科学者や政治家は平均値に基づいて政策の決定を行うようになったのだそうだ。
格差の実態をとらえるには中央値も公表すべき
しかし、今日では平均値だけで議論するのでは不十分であることを多くの人が知っている。また技術が進歩して当時とは比べものにならないほど計算能力が高まっており、大量のデータをもっと適切に政策決定に活用できるはずだ。
金融資産保有額の平均値には多くの人の資産状況を過大評価させる危険性があることは先に述べたとおりだが、この点は格差の大きい高齢者の資産について議論するときには、さらに深刻な問題だ。高齢者世帯は平均では2385万円の金融資産を保有しているが、金融資産を保有している世帯の中央値は1567万円だ。金融資産がゼロの世帯も存在することを考えると、高齢者世帯全体の保有金融資産の中央値はもっと低いはずだ。
高齢者の多くが2000万円以上の金融資産を保有しているという前提で日本社会の老後の生活保障制度を設計するのと、1500万円を下回る世帯が一般的であるとの前提で考えるのとでは、結果がかなり異なるだろう。
米国ではセンサス局から毎年、家計の所得と貧困についてのリポート(Income and Poverty in the United States)が公表されているが、そこで家計所得として議論されているのは、実質所得の「中央値」(Real Median Earnings)の動きで、実質所得の「平均値」ではない。
日本は所得格差が小さい国だといわれてきたが、必ずしもそうとはいえなくなっている。ところが日本の統計は平均値あるいは日本全体の合計値を求めることを主眼にしてきたので、統計で所得格差の実態をとらえにくい。これを改善するためには、既存の統計でもっと所得分布の問題に注意を払うべきで、まず、その第一歩として所得や資産の統計で、平均値だけではなく中央値も公表していくことを提言したい。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

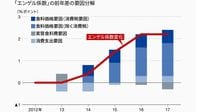





























無料会員登録はこちら
ログインはこちら