ナイキ創業者「走り続ける経営」が斬新なワケ アスリート思考に基づくビジネス感覚とは?
ランナーが走り続けるために血液の循環が必要であるように、会社を経営し続けるためにも資金繰りに奔走し、現金を回し続けなければならない。
だが早すぎる成長ゆえに、現金保有量はすぐに底が見えてしまう。その都度銀行へ行って、担当者に状況を説明する。財務表を見せて売上は倍に伸びていると説明し、資産は十分だとハッタリをかます。まさに文字通りの自転車操業なわけであるが、この走るか、死ぬかという緊張感が全編を通して通奏低音のように流れており、まったく読者を飽きさせない。
もちろんナイキが成長するにつれ、フィル・ナイト自身も成長していくわけだが、それ以上に倒すべき相手も大きくなっていく。信頼すべき取引相手であるはずのオニツカ・タイガーに会社を乗っ取られそうになったり、挙句の果てには訴訟騒ぎも起こす。借入先の銀行は資産を凍結し、詐欺案件としてFBIまで動き出してくる。またある時は、アメリカ国内での競合相手たちが結託し、ナイキの関税を引き上げることを画策した。
そんな窮地に追い込まれた彼をいつも救ってくれたのが、個性あふれる仲間たち。とりわけ共同創始者でもあったバウアーマンの存在感が光る。かつてフィル・ナイトの陸上のコーチであった男は、典型的な靴オタクでもあった。そんな彼が会社のパートナーの座にいることが、アスリートに対するベストな靴作りを可能にし、アスリート界隈への影響力を行使することも可能にしたのである。
さらに日本の総合商社・日商岩井(現・双日)も白馬の騎士のように現れる。もっとも苦しい時期に資金面でも精神面でも彼を支えてくれた日商岩井に対する感謝の気持ちは今でも大きく、ナイキの本社オフィスの中心部には、日商岩井日本庭園という場所があるほどだという。
走りのプロセスの中に喜びを見いだす術
人の記憶とは、あいまいなものである。ここ一番の勝負で成功をおさめてしまえば、その前夜にいくら不安でたまらない気持ちで過ごしていたとしても、成功の記憶しか残らない。本書は、あえてこの不安な前夜だけを抜き出して、つなぎあわせたような側面がある。思い通りにいかない環境の中で、苦しんで、もがいて、生き延びる。そのプロセスの中に、成功者のリアリティがあるのだ。
本書で描かれている話は、1962年から1980年までのことである。今で言うVC(ベンチャーキャピタル)のような存在もなければ、ネットもない。それ以上にランニングを取り巻く環境も、今とは大きく異なった。普通の人が走ることなど、珍しいとされていた時代のことである。それでも彼のランニングに対する価値観は、今の時代にもフィットするような普遍性を帯びていた。
“走る行為そのものがゴールであり、ゴールラインなどない。それを決めるのは自分自身だ。走る行為から得られる喜びや見返りは、すべて自分の中に見出さなければならない。すべては自分の中でそれらをどう形作り、どう自らに納得させるか、なのだ。”
この走りのプロセスの中に喜びを見いだす術は、ビジネスにも応用されていく。走ることと、経営すること、2つの「run」に通じるところがあるとすれば、成功とは何かの我慢と引き換えに得る一時的な快楽ではなく、目的を達成するまでのプロセスの中に見いだすものであるということだ。
つまるところ彼にとってのビジネス上のゴールは、生きることと重なりあうほどの没入感を得ることであったのだ。このアスリート思考に基づくビジネス感覚が非常に現代的であり、今を生きる多くのビジネスマンの心の中にも、静かに炎を灯してくれることだろう。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

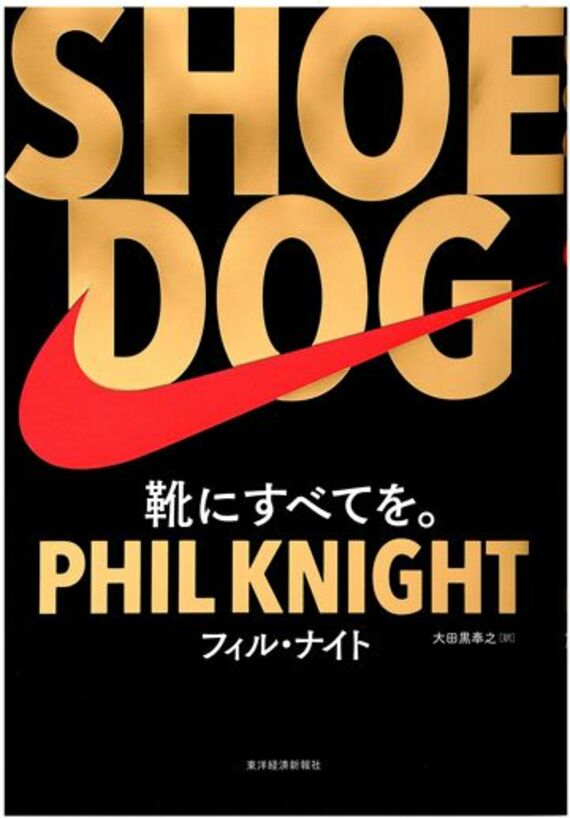































無料会員登録はこちら
ログインはこちら