風化させてはならない野村證券の「功」と「罪」 バブル最前線を知る2人が語る現代への警鐘
永野:僕は野村と40年間深く付き合ってきました。今回の『バブル』という本が時代への鎮魂歌だとすれば、田淵節也を持ち上げすぎではないかという人もいます。ただ、何かについて語るのであれば、その組織でインサイダーになるくらいに入り込まないと語れない部分もあります。大蔵省の行政と、興銀を中心とした護送船団行政がバブルの原因だということを描くために、相対的に株屋・不動産屋に対する批判は甘くなっている(笑)。

横尾:バブルというと土地と株と言われますが、当時の僕らは株ではバブルは起こらないという認識でした。いくら値上がりしようと株では迷惑かけない。企業からしたら調達コストも下がるわけです。土地は上がるほど生産コストも上がりますし、住居費も上がる。その意味でわれわれは不動産とは違うんだという意識がありました。
永野:その株屋さんの意識は、大衆に伝わっていなかったんですね。
横尾:上がった分が、お客さんにきちんと利益として反映していたかどうかについては、問題がありました。
永野:僕が記者時代に言い続けていたのは、個人金融資産が大事な時代がやってくるということ。企業同士の株式持ち合いが解消されると、株と不動産は、個人金融資産の中で有力な投資対象になるという認識だった。右肩上がりの土地政策を維持しないと、革命が起きてしまうというのは、大蔵省でも思っていたこと。
横尾:土地と連動して上がる銘柄株もあれば、反対に動く株もあります。バブル時代はそれが全部一緒に上がると思っていたのが間違いです。銘柄の選択眼がまったくなかった。みそもクソも一緒にやってしまった。
アメリカから見るとバブル崩壊は予想できた
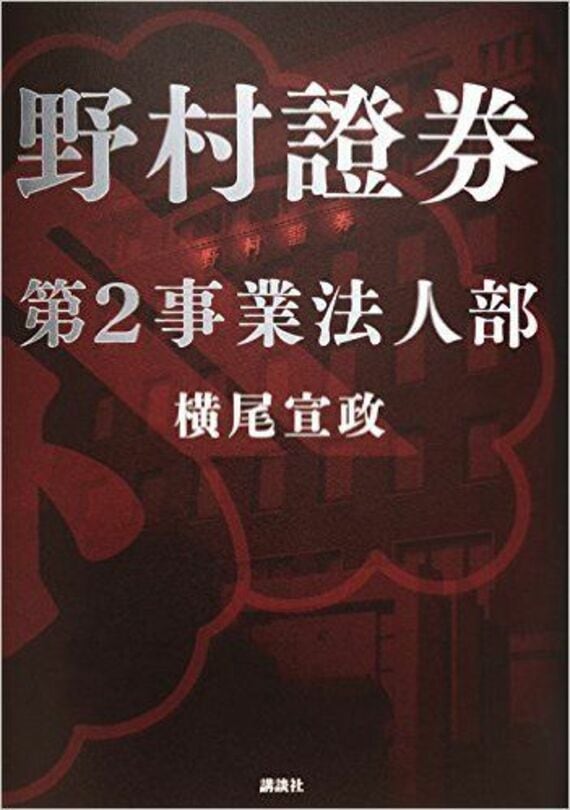
永野:何で僕が1989年まで、実際には1992年に宮沢喜一さんが公的資金投入の機会を逃すところまでを描いたかというと、それまでは、土地は暴落していなかったから。三井住友銀行頭取だった西川善文さんが『ザ・ラストバンカー』で書いてくれたように、あのときに公的資金を投入してくれていたら、傷口はここまで大きくならなかった、という気持ちはよくわかるのです。
横尾:僕は1988年10月に第2事業法人部から野村企業情報に出向し、初めて株価ボードから離れました。日経平均が3万4000円くらいの頃、この相場はおかしいと、事業法人部の仲間に、「全部株を投げろ」と伝えましたが、逆にそこから数カ月がすごかったですね。永野さんの本でも触れられていますが、あの頃から1989年末にかけて完全に状況が一変しました。1990年春にアメリカに転勤し、外国から見ると、日本の土地の状況はまずいと思い、持っていたリゾートマンションを売りました。































無料会員登録はこちら
ログインはこちら