
世界経済が長期的な停滞期に入ったのか、それとも今まさに大躍進を遂げようとしているのか。2013年のサマーズ元財務長官の講演がきっかけで議論が活発となったが、見方は大きく分かれている。
Cowen(2011,注)のような悲観的な見方では、低い樹になる果実のように比較的簡単に手に入れることができる発明や発見はこれまでに収穫されてしまい、残された科学や技術的な課題は容易には解決できないものばかりだとする。今後は、科学技術がこれまでのように急速な発展を遂げることは期待できず、必然的に経済成長はゆっくりしたものになるのは避けられないと考える。
他方、IoT(Internet of Things)であらゆるものがインターネットに接続することやAI(人工知能)の発展で、経済・社会が飛躍的に発展するという予想もある。囲碁の世界トッププロを人工知能が破ったように、コンピュータが人間の能力を完全に超えることも視野に入った。世界中の自動車会社が自動運転技術の開発にしのぎを削っており、遺伝子工学を使った再生医療などが進歩して、これまで治療が難しかった病気やケガも治せるようになるなど、世界が大きく変わるという見方も多い。
経済成長が止まってしまうことはない
大恐慌下にあった1930年代のアメリカで経済発展は必然的に停滞に至るという長期停滞論が唱えられたものの、第二次世界大戦後の世界経済の発展によってこうした悲観論は忘れ去られていた。再び悲観論が否定されることになるのかどうかは、歴史の判定を待つほかはないが、楽観論が描く未来を実現するためには、人間社会が急速な技術の変化についていけるように努力する必要がある。
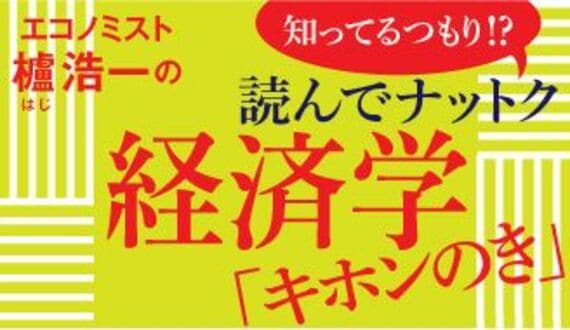
経済学で言う技術進歩には、科学・工学的な技術のみでなく、企業経営や労務管理など直接生産に関わるものも入るし、法律や規制、人々の生活スタイルなど、社会の幅広い変化も含まれている。
今後AIが進歩すれば多くの職がコンピュータに取って代わられてしまうという懸念が高まっている。技術の進歩が遅いことよりは、むしろ技術の進歩でおこる経済社会の変化に我々がついていけないことのほうを心配すべきだろう。
二度にわたる世界大戦からの復興も加わった1950〜60年代のような高い経済成長を期待するのは無理だが、経済成長が止まったり経済が衰退したりしてしまうと考えるのは悲観的に過ぎる。
































無料会員登録はこちら
ログインはこちら