「データセンターが水を奪う⁉」 AIインフラ爆増の裏側でグーグルが隠蔽した"水使用量"
契約にはさらに条件がありました。それは、グーグルに対して一定の水道使用量を優先的に割り当てる代わりに、同社が水源拡張工事に2850万ドルを負担するというものでした。
しかし、この「一定の水道使用量」がどの程度の量なのか不明確だったことから、市民の間で不安が広がりました。やがて情報公開を求める運動が活発になっていきます。
地元有力紙オレゴニアン(The Oregonian、オレゴン州ポートランドで発行)は、2021年10月、グーグルの水使用量の開示を求める書簡をワスコ郡の検事総長に提出しました。
検事総長は市に対して開示を命じましたが、ダレス側はこれを拒否。「グーグルの水使用量に関する情報は企業秘密であり、情報公開義務の適用外である」と主張し、逆にメディアに対して訴訟を起こしました。
世界中のデータセンターにおける水使用量を公表
法廷闘争は約1年に及びました。最終的に2023年2月、和解が成立し、ダレスはグーグルの過去10年分の水使用量を公表しました。公開されたデータによると、2012年には43万5000立方メートルだった水使用量が、2022年には146万立方メートルに増加しており、市全体の使用量の29%を占めるまでになっていました。
このケースは、テクノロジー企業の水利用に関する情報開示のあり方に一石を投じました。
グーグルはこの件を機に、ダレスだけでなく、世界中のデータセンターにおける水使用量も公表するようになりました。
たしかに、グーグルの水利用は契約に基づくものであり、同社は地域の水インフラに多額の投資も行っています。とはいえ、このような「水の優遇」が、地域にとって本当に望ましい選択なのかは慎重に検討されるべきです。一部の住民からは「グーグルは水の吸血鬼だ」といった批判も上がっており、短期的な経済的利益と引き換えに、地域の将来にリスクを抱え込む可能性も否定できません。
テクノロジー産業は、経済的な恩恵を地域にもたらすだけでなく、水という目に見えにくい共有資源にも影響を及ぼしています。データセンターの増加により、水の優先順位を再検討せざるを得ない地域が増えていくでしょう。
私たちが日々利用しているインターネットの背後で、どれだけの水が使われているのかを意識することは、これからますます重要になるはずです。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

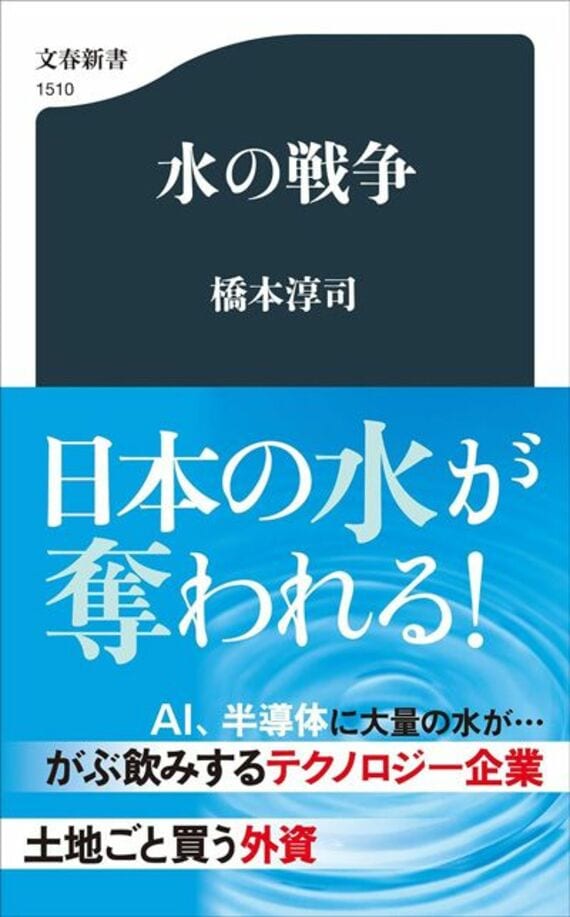
































無料会員登録はこちら
ログインはこちら