マレーシアで生活する以上「英語」が共通言語のひとつになりますから、先生や学校のスタッフ、賃貸物件のオーナー、さらに、生活インフラを担う携帯会社、水道会社、電力会社などとのやりとりも英語で行う必要があります。
最近は翻訳アプリも精度が高く、極論英語が話せなくてもテキストベースでコミュニケーションができますが、電話や対面など相手とリアルタイムで交渉しようとすると、聞きたいことの半分も聞けず、言いたいことの半分も言えない、という歯がゆい思いをすることも。
やはり「言語の壁」は生活するうえでの大きなストレス要因のひとつと言えるでしょう。
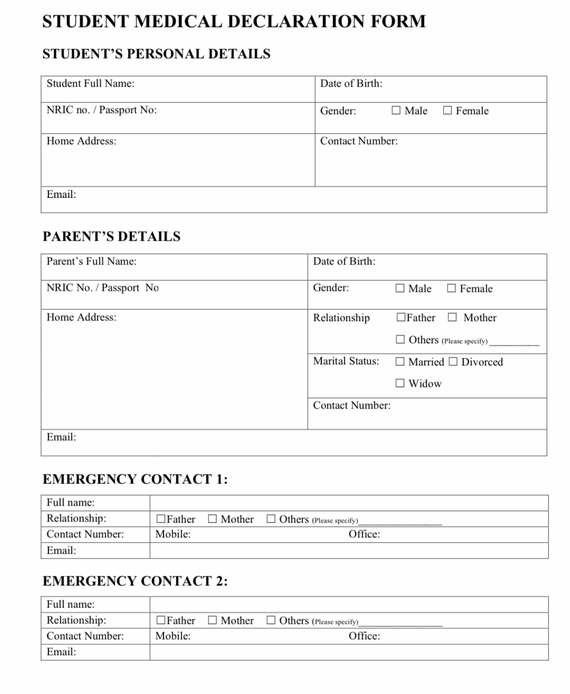
日本の水準・常識を求める
「家のつくり、掃除のきれいさ、時間管理や応対の丁寧さなど、日本の品質やサービスレベルをマレーシアで求めてしまう方は、ストレスを多く感じるかもしれません」(前出の藤井氏)
たとえば我が家が借りたコンドミニアム高層階の部屋は、大雨の日にガラス張りの角部屋から雨水が染み込み、部屋中水浸しになりました。
そもそもの施工の甘さも問題なのですが、対応自体の遅さも日本のサービスに慣れていると非常にストレスです。
オーナーからも何度もコンドミニアムのマネジメントに急いで修繕するよう交渉してもらいましたが、修繕されたのは結局、半年後。それまではいつ浸水するかわからないので、該当の部屋に荷物を広げることができませんでした。
































無料会員登録はこちら
ログインはこちら