油業界を縛っていたルールを乗り越え、親会社から"海賊"と呼ばれた「出光」創業者の驚くべき豪胆
特約店にはそれぞれに販売担当エリア、つまり"縄張り"があったのだ。そのため、出光が下関ではなく門司に店を構えていることがネックになった。
黙認された佐三の「海賊」稼業
佐三の軽油を使う漁船が増え始めると、出光商会の親会社の日本石油には客をとられた特約店から縄張りを守るように苦情がぶつけられる。だが、佐三は船に軽油を積み込み、漁船が港に着く前に海上で売った。
そして、「陸の上では売りません。海の上なら問題はないでしょう。海の上に下関だ、門司だと境界線でも引いてあるのですか」と押し切った。日本石油側も「それでは出光は海賊だということにしておこう」とそれ以上強くは追及しなかった。
佐三が燃料として目をつけるまで、軽油は役立たずの倉庫の場所取り、厄介者扱いで、そんな軽油の需要を開拓したことは出光商会だけでなく、日本石油やひいては業界全体にとって大きなメリットだったのである。
出光商会が漁師たちから支持されたのは、客の便宜を図る営業努力の賜物だった。日本石油はそうしたことも含めて佐三の「海賊」稼業を黙認したのだった。
結果、出光商会は山神組所属の全漁船をはじめ、下関周辺の動力船の大部分に軽油を販売するまでになったのである。
ややのちの話になるが、大正12年(1923)に出光はそれまでの缶入りの油の販売から、計量器付きの船での海上給油という画期的な販売方法も開発している。船上計量器自体を発明したのも出光商会で、この新しい販売方法は顧客から喜ばれ、その後は各社がこのやり方を採用するようになった。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

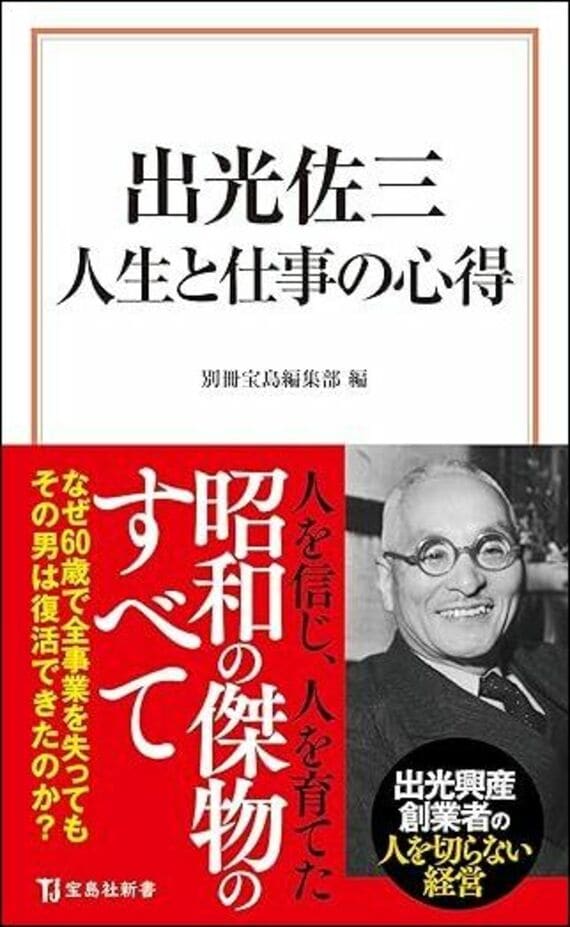































無料会員登録はこちら
ログインはこちら