NHK大河ドラマ「豊臣兄弟!」で注目…弟・羽柴秀長が「秀吉の後継者」と目されるまでの"道程"をたどる
こののち秀吉は、一門衆・諸大名・直臣らに官位を与えていくが、それは豊氏長者(ほうしのちょうじゃ)として朝廷に推挙する体裁をとり、そのため叙任者の姓は、基本的には豊臣に改姓されていくことになる。
秀長が新たな本拠・郡山城に入る
秀長が四国から帰陣したのは天正13年8月22日か23日のこととみられるが、そのとき、秀吉は佐々成政の討伐のため越中に出陣しており、26日に佐々成政を降伏させ、大坂城に出仕させている。
一方、四国平定を果たした秀長は、同年閏8月19日に秀吉から新たに大和を領国として与えられ、同国の郡山城を本拠とすることになった。秀長は、それまでの紀伊・和泉二ヶ国に加えて、大和を領国としたことで、その領地高は73万4千石にものぼるものとなった。
この領地高は、単独では秀吉配下で最大のものであったが、大和についても紀伊・和泉の場合と同様に秀吉直臣の所領があり、それらについては秀長の支配から外されていた。
同年9月3日、秀長は、秀吉とともに約5千人の軍勢を率いて大和に入部し、郡山城に入った。秀吉は5日に奈良の春日社(かすがしゃ)を参詣したのち、大坂に帰還している。
同年9月末、秀長は、秀吉の天皇居所への参内に供奉(ぐぶ)するため上洛した。昇殿(天皇居所に上がること)するには公家の身分が必要で、四位以上の位階か侍従以上の官職が必要であったことから、同年10月に、秀長は参議(宰相)と近衛中将に任官し、従三位に叙せられたようだ。
それは武家では、関白秀吉、内大臣織田信雄に次ぐ地位であった。以後、秀長は「羽柴大和宰相」と称された。
この時期、奈良では「秀長は菊亭晴季(はるすえ)の養子になった」あるいは「秀吉が新王(天皇に代わる国王)になり、秀長は関白になる」といった噂が流れた。これはまったくの誤情報であったが、このことから、世間では秀吉の後継者は秀長であると目されていたことが読み取れる。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

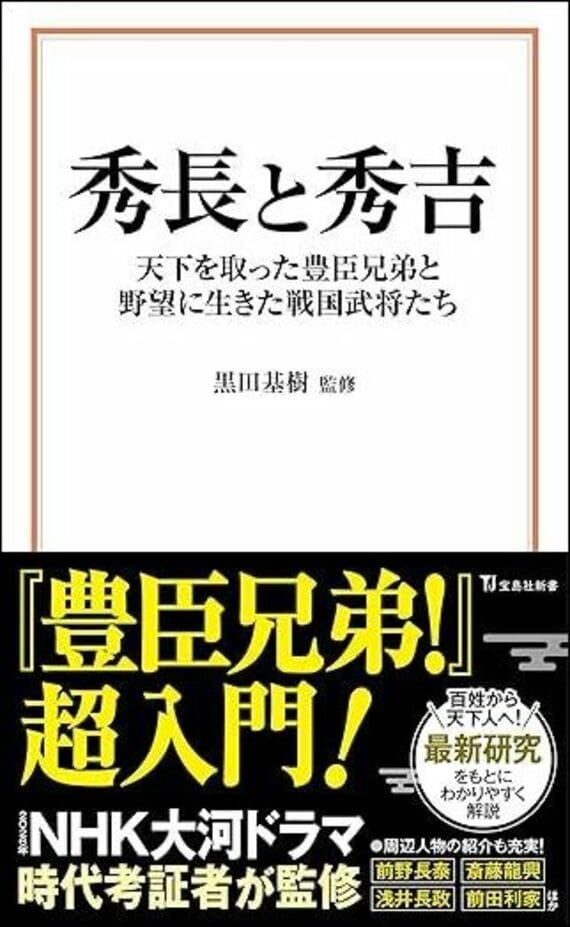






























無料会員登録はこちら
ログインはこちら