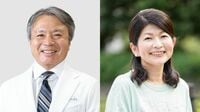白井:要するに、日本の教育にはずっと、一度つまずいたらそれっきりという人たちが一定数いたということです。義務教育を受けたことになっているけれど、簡単な文章が読めないとか、計算ができないとかいう人を大量に生み出してきた。また、今は「落ちこぼれ」ではなく「吹きこぼれ」という言葉も生まれていますが、もともとの学力や学習意欲の高い子どもたちもまた、「授業がゆっくりすぎて集中できない」と感じていることがあります。一斉授業の進度に合わせられないと、学校が楽しくなくなってしまう。これは私たちが子どもの頃から変わっていません。
マジョリティになれないと学校が楽しくなくなる
窪田:白井さんとプライベートでお話しするときにも、子ども時代のことや発達の特性のことはよく話題に上りますね。私たちも勉強はできましたが、先生の話を聞いていなかったり席に座っていられなかったりと、授業に集中できない子どもでした。
白井:おっしゃるとおりです(笑)。それでも、昔は不登校の子どもが少なかったのはなぜか。同調圧力が今日の比ではなかったことも一因ですが、結局のところ、ほかの選択肢を知らなかったということに尽きると思います。
窪田:日本では公立の学校に通う場合、単純に住んでいるエリアで通学先が決まるという仕組みが今も続いています。私が以前住んでいたシアトルではそうした制約はなく、学校を自由に選ぶことができました。日本でも、こうした形のほうが望ましいのでしょうか。