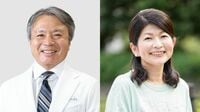それまでは、子どもたちの教育に関する法律は、全員が通学することを前提としたものしかありませんでした。2017年に同法が施行されたことで、不登校をはじめ、さまざまな理由で学校に通えない子どもにも、やっと目が向けられることになったのです。
不登校の増加はコロナ禍後ペースアップ、今は34万人に
そこから約10年が経ちますが、まだまだ法律は浸透しておらず、周知も足りないと感じています。しかし、文部科学省の調査では、小・中学校における不登校の児童・生徒の数は、34万人を超えています。つまり、34万以上の子どもたちの学習の機会が、まだまだ不安定な状況にあるということです。
窪田:それはすごい数ですね。白井さんが活動を始めてから26年になりますが、その頃から今に至るまで、不登校の子どもの数は一貫して増えているのですか?
白井:そうです。とくにコロナ禍以降、年間5万人という速いペースで増加を続けています。
窪田:しかも、少子化で子どもの数自体は減っているのに、不登校者の数も比率も増え続けているのですよね。その原因はなんなのでしょうか。
白井:いろいろあるので一概には言えませんが……いちばん大きな理由は、身体のつくりも脳のつくりも個人差が大きく、子どもは非常に多様であるということだと思っています。それなのに、日本の学校には一斉授業と軍隊式の名残のような教育が今もあります。みんなが同じ時間内で理解しなければならず、周囲と同じように振る舞うことが求められる。一度つまずくともうそこで置いて行かれてしまい、自力で追いつくことは難しくなります。大人だって得手不得手があるのに、これは子どもにとってはかなりきついことだと思います。
窪田:確かにそうですね。しかし、日本の教育はずっとその形でやってきたというのも事実です。これについてはどうお考えですか。