戦後、【立派な戒名】が庶民に広まった背景には、「死してなおスター」の"まばゆい存在感"があった
しかし、戦後の日本とは、石原や美空のような"実力で成り上がった人間"が、その財力で自由にふるまえる時代だったのだ。
「死してなおスター」が与えた影響
一方で、これは21世紀になった現在でははばかられることだが、こうした有名芸能人などといった、いわゆる公人的存在は戦後の一時期まで、プライバシーなどないも同然の扱いをメディアからされることがあった。
いかに政治家や芸能人などであっても、遺族にしてみれば葬式くらい、身内だけでしんみりとやりたいものだろう。実際に最近では、「葬儀は身内だけで執り行い、後日あらためて『お別れの会』を開催」といった流れが、著名人であっても一般的になっている。
しかし、石原や美空が死去した当時は、そんな時代ではなかった。彼らの葬儀はワイドショーなどによって生中継されており、それを多くの人々が見た。まさに彼らは死してもスターだったわけだ。
そして、そういう流れは葬儀の世界にもある変化を生んだ。彼ら著名人の葬儀を─テレビなどを通じてだが─間近に見て、その"立派な戒名"などをも目にした一般市民たちも、また居士や院号などの戒名を欲するようになっていったというのだ。
寺や葬儀社側も、とくに断るようなことでもなく、かくして戦後の日本人は"立派な戒名"を誰でも付けるようになった……という話が、お寺や葬儀業界の周辺ではよく言われているのである。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

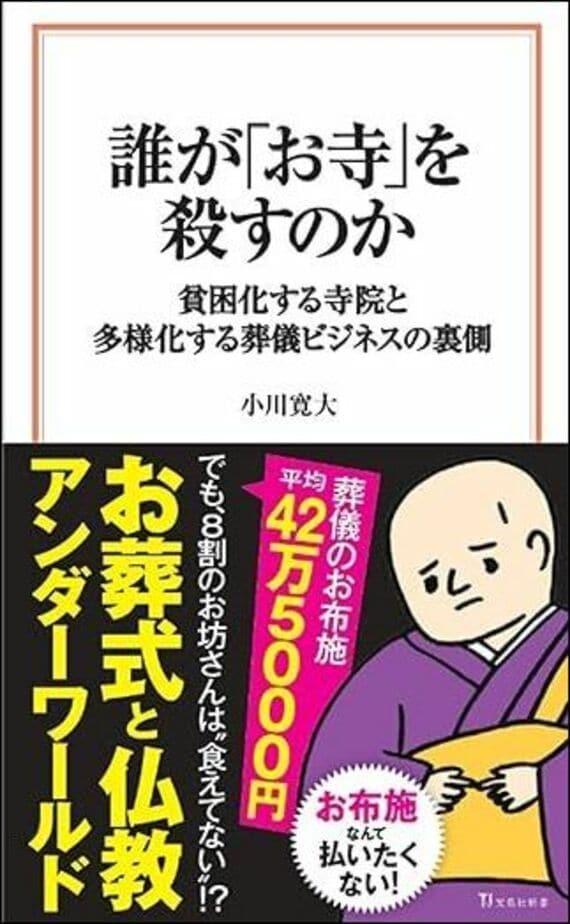






























無料会員登録はこちら
ログインはこちら