気をつける点はたったの2つ…「特殊な訓練なし」で読書スピードが劇的に向上する《高速読書》の凄さ
つまり、どのような本でも(それが小説や日記風のエッセイでない限りは)、著者の主張とそこから分岐する論点だけを把握すれば、本の内容をほぼ理解することは可能です。そこから行き着いたのが、これからみなさんに紹介する「つまり読み」です。
頭の中で「つまり何?」とつぶやきながら読む
これは、私のコンサルティング経験から生まれた読書法です。コンサルタントは結論を先に伝えて、説明を簡潔にしなければなりません。そのトレーニングとして、私は社員に「声に出さなくてもいいので、頭の中で"結論を先にいうと"とつぶやいてから説明を始めなさい」と教えています。
すると、不思議なことに、どのような新人でも結論から話を組み立てることができるようになります。たとえ心の声であっても、脳はその言葉に引っ張られて、結論から話し始めてしまうというわけです。
これと同じで、頭の中で「つまり何?」とつぶやきながら本を読むと、大切な部分とそうではない部分が無意識に区分できるようになります。
結局のところ、著者は何を言いたいのか。接続詞のところでも述べたとおり、主張や結論のある場所はたいてい決まっていますので、把握するのはそれほど難しいことではありません。
□「結論」を支える論点やポイントはどうなっているか(構造)
□結論を中心に構造を理解する。
「つまり読み」を始めてから、目的が明確なら本の内容の半分は捨てていいんだと気づきました。そこから、私は速く本を読めるようになりました。
目的に沿わないところは削っていい。読まなくていい。内容を絞れば、それだけ記憶にも残る。計画や行動に時間を使える。そのことに気づいた。そのうえで「つまり何?」と結論を探しながら本を読むようにすることで、どんどん速く読めるようになったわけです。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

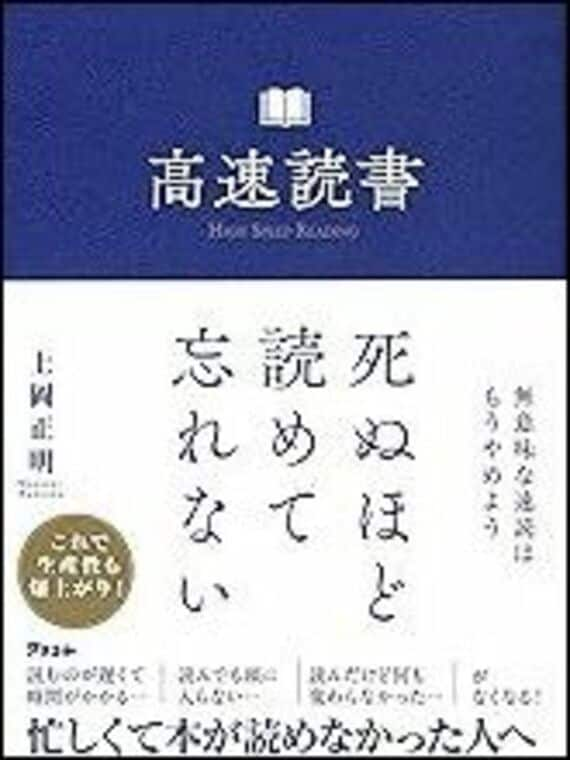






























無料会員登録はこちら
ログインはこちら