「ボクシング試合で2人死亡」から考える"コンタクトスポーツと脳の安全性"――研究でわかったリスクと脳を守る対策《医師が解説》
注意しておきたいのは、これまで述べてきたリスクを踏まえても、多くの専門家が「適切な管理の下でのコンタクトスポーツ継続を推奨している」点です。
実際、デンマークで約8500人を25年間追跡した研究では、最も長生きだったのがテニス選手(平均9.7年延命)で、次いでバドミントンですが、コンタクトスポーツのサッカーが3位に入るなど、仲間と一緒に行うスポーツが上位に並びました。
それでもスポーツはメリットが多い
研究者は、体力向上に加えて、スポーツを通じた仲間との交流が、心身の健康に大きな効果をもたらすと指摘しています。また、運動不足や社会的な孤立が認知症に与える悪影響は、スポーツによる脳外傷リスクを大幅に上回ることもわかっています。
単に「危険だから避ける」のではなく、科学的な根拠に基づいて安全性を高めながらコンタクトスポーツを続けることが重要です。海外の研究では、適切な対策により脳外傷のリスクを30〜40%削減できることが示されています。
今回の後楽園ホールでの事故はプロスポーツの興行で起こったことであり、子どものスポーツと一緒にしないほうがいいという考え方も、もしかしたらあるかもしれません。
しかし、これを教訓にし、日本でも保護者、指導者、医療関係者、スポーツ団体が一体となって一層の安全対策に取り組む必要があります。
プロボクシングの現場はもちろん、学校や地域のスポーツ現場でも、海外の成功例に学び、日本の文化や環境に合わせた安全対策を今以上に導入すれば、コンタクトスポーツをより安心して楽しめる環境を作ることができるでしょう。
そして、競技での成果と長期的な脳の健康は決して相反するものではないことを、スポーツ界全体で共有していく必要があります。
最新の医学的知見を活用し、世界で進む安全性向上の流れを日本でも積極的に取り入れることで、若いアスリートたちがスポーツの魅力を十分に味わえる未来を築いていくことができるはずです。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

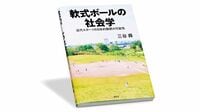





























無料会員登録はこちら
ログインはこちら