「ボクシング試合で2人死亡」から考える"コンタクトスポーツと脳の安全性"――研究でわかったリスクと脳を守る対策《医師が解説》
令和時代の学校の部活動や地域のスポーツクラブでは、昔ながらの「根性で乗り切れ」「少しくらい痛くても我慢しろ」といった指導方法は少ないでしょうが、最新の科学的な安全対策の導入は必ずしも追いついていない面がまだあるでしょう。
また、指導者の多くは競技経験を豊富に持っていても、最新の医学知識については詳しくない場合が多く、適切な研修が急務となっています。
プロボクシングのようなスポーツでは医師の立ち会いがありますが、学校や地域のスポーツ現場では、そうした医療体制は必ずしも十分ではありません。
欧米では既に導入が進んでいる脳震盪の早期発見システムや、段階的復帰プログラムの整備も、日本ではまだ発展途上の部分があります。
親や指導者が気をつけたいポイント
一般のアマチュアスポーツの現場でも、お子さんがコンタクトスポーツをする際には、親や指導者が気をつけるべき具体的なポイントがあります。
●脳震盪の対応ルールがあるかチェック
まずは万が一に備え、所属するチームや学校に脳震盪の対応ルールがあるかを確認しておくのがよいでしょう。
たとえば世界保健機関(WHO)と国際サッカー連盟(FIFA)のキャンペーンでは、頭痛、めまい、吐き気、記憶障害、集中力低下、光や音への過敏、睡眠障害、感情の変化といった症状のうち、1つでも該当すれば即座に競技から外れるべきとしています。
試合や練習での頭部衝撃後、これらの症状が15分以上続く場合は医師の診察が必要です。また、意識消失、繰り返す嘔吐、激しい頭痛があれば、救急搬送が必要な危険信号です。
●コンタクト回数を制限しているかチェック
競技別の具体的な対策としては、例えばサッカーでは、小学生年代のヘディング練習を高学年から段階的に開始し、月4回以下、1回の練習あたり10回以下に制限することで、従来は数百回以上ともいわれていた年間頭部衝撃回数を、40〜60回程度に削減できます。
中学生以上でも週1回、1回の練習あたり15回以下の制限により、脳への累積ダメージを大幅に軽減できます。
ラグビーでは、タックル練習の時間を週3回の練習のうち1回のみに制限、1回の練習でのタックル回数を15回以下、といった形にすることが推奨されています。
また、フルコンタクト練習は週1回以下に抑え、残りはタッチラグビーなど接触を避けた技術練習に重点を置くことで、技術向上と安全性の両立が可能になります。

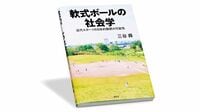





























無料会員登録はこちら
ログインはこちら