「ボクシング試合で2人死亡」から考える"コンタクトスポーツと脳の安全性"――研究でわかったリスクと脳を守る対策《医師が解説》
イングランドでは、10万人を超える子どもを対象とした調査をきっかけに、2024年から小学生年代のサッカーで意図的なヘディング練習を原則禁止しました。中学生以上でも週1回以下、1回の練習で10回以下に制限しています。
この対策により、年間の頭部衝撃回数を従来の数百回から数十回レベルまで減らすことに成功しています。
アイルランドのラグビーでは、タックルの高さを肩から胸の下に制限する試験を2シーズン実施し、頭部への衝撃が30〜40%減少したため、この対策を継続することを決定しています。
NFLでもタックルのルールを変更し、キックオフの方法を改善した結果、選手の脳震盪(のうしんとう)件数が17%減少し、データ集計を開始した2015年以来、2024年シーズンには最も少なくなりました。
また、注意喚起することで、2012年から2018年にかけて、コンタクトスポーツによる小児の救急外来受診が32%減少したという成果も報告されています。
脳震盪への治療法は大きく進化
脳震盪の治療法も大きく変わってきています。
以前は「暗い部屋で完全に安静にする」ことが常識でしたが、最新の研究では、危険な症状がない限り、早めに軽い活動を再開するほうが回復を早めることがわかってきました。
新しい治療プロトコル(手順)では、24〜48時間後から段階的に活動を再開することになっています。
第1段階は15分程度の軽い散歩、第2段階は20〜30分の軽いジョギング、第3段階は接触のないスポーツ練習、第4段階は通常の練習参加、そして最終的に試合復帰という5段階のプロセスを踏みます。
各段階で24時間以上症状が出ないことを確認してから次に進み、症状が出たら前の段階に戻ります。
この方法により、多くの若いアスリートが2〜4週間で完全復帰を果たし、従来の無期限安静と比べて、復帰期間を平均30〜50%短縮できることが報告されています。
ただし、子どもや10代の選手は大人より回復に時間がかかり、長期的な影響も受けやすいため、成人より1.5〜2倍長い期間をかけて慎重に判断することが推奨されています。
日本でも2019年のラグビーワールドカップや東京オリンピックを機に、スポーツ安全への関心は高まりました。しかし、安全対策が十分に普及したとまではいえないのが現状です。

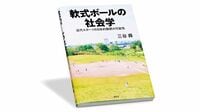





























無料会員登録はこちら
ログインはこちら