
姉妹でも別姓、子どもの反応は
親子で姓が違うことで、教育や医療の場面で問題が生じることはないのだろうか。
「保育園や小・中学校には、私たちが事実婚であることを説明していますので、問題が起きたことはありません。離婚や、子連れで再婚をされているご家庭が事実婚よりも相当数いらっしゃいます。学校側もそういった背景を想定して対応することに慣れているのではないのでしょうか。
また、病院については、最初に近所のかかりつけの小児科に、家庭事情を説明しました。そこでご理解をいただいたので、私が親権者ではない長女を、妻が次女を連れていっても問題はありませんでした。
一度、かかりつけ医から紹介状をもらって次女が大きな病院で診察を受けた際も、妻の付き添いに何の不都合もありませんでした。おそらく、紹介状にそうした事情が記載されていたのだと思います」(水口さん)
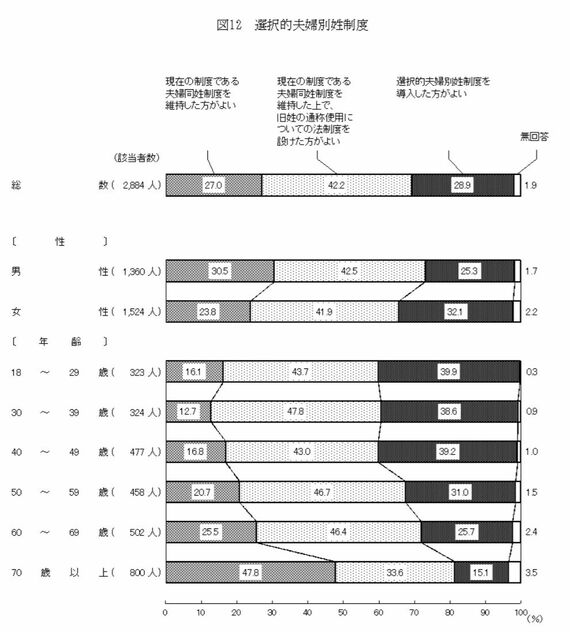
































無料会員登録はこちら
ログインはこちら