企業はどのように対応すべきか
このような状況において、企業はどうすればいいか。私は別記事で、企業全体での対応を求めた。それに加えて下記を記す。
・各国の情勢や確認漏れがないようにする:もしかすると日本国内のウェブ関係者と、中国、台湾、香港等の担当者が連携していない可能性がある。そこは政治的な内容を含めてチェックリストを共有したいところだ。
・組織内コミュニケーションを欠かさない:表記の統一や、そもそもどのような表記にするかどうかはトップの判断により規定される。後手後手の対応になると、さらに火に油を注ぐことになる。早急な対応をするためにもトップ主導のコミュニケーションが望まれる。とくにグローバルポリシーは広報部門だけで担えるものではないため、経営側からの明確な社内向けメッセージが重要になるだろう。
ところで、私が思うのは、各企業の担当者は矛盾を感じているだろうな、ということ。というのも、各社の謝罪文を読んで感じるのだが、「誰に対して、何を、どのような理屈で謝っているか」がわからない。
たとえば、台湾を中国と記載して謝罪するとする。その時、本音をそのまま書くとしたら、「いやあ、日本政府の正式見解でも、『一つの中国を主張し、台湾は中国の一部だとする……という中国の立場を理解、尊重する』というふうになってはいるんですけれど、まあ、あれですわ。私たちは台湾を、思想の近い“国”と思っているわけで、難しいですねえ。だから、台湾を中国と称することに非難が届くのも理解できるって言うか、まあ、そうですねえ、総合的にいえば悪かった、と言える可能性は否定しませんねえ。少なくとも、絶対的に弊社が悪いかは判断を保留しますが、騒がせた事実だけは悪かったとも言えるわけで……」という、ゴニョゴニョとした内容になるに違いない。
もはやこんな謝罪文を掲載するメリットはない。ゆえに、「誰に対して、何を、どのような理屈で謝っているか」がわからない謝罪文になるのだ。
しかし、それは収益と利益を最大化する企業の立場からすると当然といえる。高度な曖昧戦略、高度な二枚舌戦略を取らざるをえない。正しさは一旦脇に置いて、企業としては台湾も中国も、両方の顧客を大切にしなければならないのだ。
もちろん、そのせいで、どっちの側からも「裏切り者!」と指をさされるかもしれない。そして、それはグローバル市場でメシを食っていくための、必要なコストなのかもしれない。これからの時代に重要なのは、正しさを断言できないグレーゾーンこそ考え抜いて、「全員から賛同はされないけれど、この路線で行こう」という決断なんだと私は思う。
結論。企業はギリギリの線で頑張っている。なので、日本企業に対してはできれば優しくみてやってほしい。

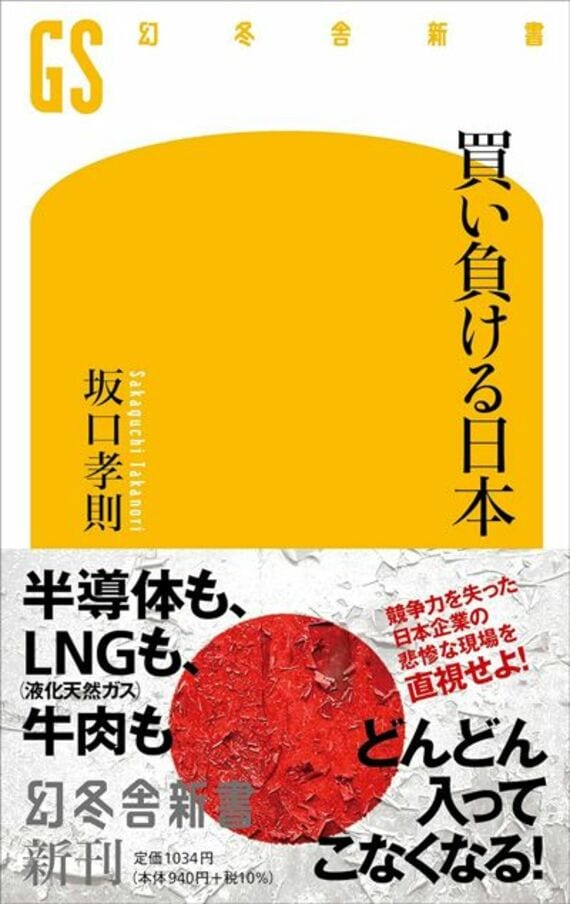



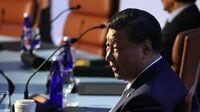


























無料会員登録はこちら
ログインはこちら