「リスクのある手術か、投薬か」人生の“究極の選択”で重視すべきこととは?《ノーベル賞受賞者》が考案した「決断」の賢い方法
宗教家や星を信仰する気持ちがどれだけ強くても、よその農家の作物が自分の作物の背丈を追い越している姿や、よその畑は豊作で自分の畑は不作である状況を目の当たりにすれば、信仰心を保っていられなくなる。
科学者でない人こそ、科学的思考を身につけるべき理由
科学の素晴らしいところは何と言っても、“役に立つ”ところだ。科学が私たちの日常生活にどれほど入り込んでいるかは、あらためて説明するまでもない。
私たちが口にする薬や食べ物をはじめ、運転する車も、頼りにしているインターネットも、すべて科学の賜物だ。これについて異論を唱える声はまずあがらないだろう(それどころか、情報が氾濫するなかで科学に関する荒唐無稽な主張の多さが問題視されていて、その内容は「ワクチンにマイクロチップが埋め込まれている」「電灯が太陽に取って代わる」など多岐にわたる。科学があまりにも多くの偉業を成し遂げ、凄すごいことができて当然と思われているせいで、ありえそうにないことができると提示されても、あながち嘘とは言い切れないと感じる人が大勢いるのだ)。
科学は魔法ではなく、設計によって機能するものだ。そして、魅力的だがまったく科学的でない話に騙だまされることから人々を守ってくれる。
人はみな、生まれ持ったバイアスから逃れられずに苦労しているが、科学はそういうバイアスの影響から身を守るテクニックもいろいろと発展させてきた。それは「個人の感情を交えずにすむ」テクニックで、エビデンスを評価する必要性が生じても、そのテクニックを使えばおおむね機械的に評価できるので、使う人の心理が影響を及ぼすことはない。
そうしたテクニックは科学全体で共通していて、分野によって呼称が違っても、中身は同じだと周知されている。まだ使っていないという人は、絶対に知っておいたほうがいい。
そういうテクニックは科学といっても、ロケット科学のような科学とは別物だ。決して難しいものではないし、計算も必要としない。このテクニックを身につければ、科学者かどうかを問わず、誰もが科学者の言葉に興味を持って耳を傾けられるようになる。
たとえば、分子生物学の分野に身を置いて、人体に存在する特定のタンパク質の作用を専門に研究する科学者がいるとしよう。そういう分野の科学者でも、発達心理学(子どもが算数を習得する経緯などを追究する学問)
の実験研究を考察することや、実験の設計の論理を理解することはできる。なにも分子生物学の研究を通じて、子どもの学び方に関する特別な知識をあれこれ得られるわけではない。発達心理の実験研究に数理解析が関係する複雑さがあるとは思えないので、数学的なスキルも関係しない。
そういう話ではなく、分野が違っても理解できるのは、すべての実験が科学の分野を問わず同種の問題を抱えているからであり、すべての科学者が同じバイアスの影響を防ぐ必要があるからだ。
そのためのテクニックの習得は、科学を専門的に学んでいない人にとっても難しいことではない。それどころか、正式な学校教育をそれほど受けていなくても問題ない。
それに、学術研究以外の場面でもそういうテクニックは必要不可欠で、たとえば、「子どもに何を食べさせればいいのか」「ワクチンを打つべきか」といった非常に身近なことについて考えるときにも役に立つ。
バイアスの影響を防ぐテクニックを体得しても、科学者が行う実験を再現できるようにはならないし、習得に何年もかかる専門的な知識が身につくわけでもない。
だが、誠実な仕事かどうか、自分を真実に近づけてくれるものかどうか、耳目を集めて人に巣食う偏見を煽るだけの作り話かどうかを見極める力はつく。本物の専門知識と偽りの専門家の区別がつくようになる。そういうことができる力、すなわち、科学的な思考を促すテクニックやツールを、自分のものにしてもらいたい。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら





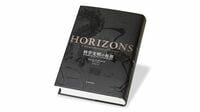


























無料会員登録はこちら
ログインはこちら